季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
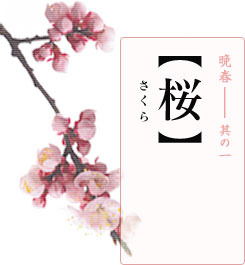
春を代表する花は、日本では桜そして梅ということになる。ところが俳句歳時記で「花」の項をひくと、花一般をさすのではなく、桜に限定されている。つまり花といえば桜のことで、「花の雲鐘は上野か浅草か」(芭蕉)の花も「人体冷えて東北白い花盛り」(金子兜太)の花も桜なのである。
いつ頃からこのようなことになったかというと、中古・王朝時代からのようだ。それ以前はむしろ梅のほうが優勢だった。「万葉集」で詠まれた花のランキングを調べてみると、1位は萩で141首、2位が梅の118首、3位は松、4位は藻、5位は橘、6位は菅、7位は薄、そして8位に桜の40首あまりが位置する。梅のほぼ3分の1ほどしか詠まれていないのである。これが「古今集」になると、桜の53首に対して、梅は29首と逆転する。
その理由としては、まず桜が日本にもともと在来し、東アジアに広く分布していたのに対して、梅は橘などと同じく中国原産で、奈良時代以前に渡来したものだという事情がある。外来のものへの好奇心や憧れは今日の私たち以上に強いものがあったはずで、梅は中国文化を象徴するものとして、当時の貴族たちの憧れの的となったのである。ちょうど明治以降のバラに対する日本人の嗜好には、西洋文化への憧れが濃厚に含まれていたのと同じである。
桜は観賞用というよりも、当初は実用性において認識されていたようだ。福井県の鳥浜遺跡からは、5千年以上も前の縄文前期の弓が多数出土しているが、その中に桜の樹皮を巻いて補強しているものが発見されている。桜の樹皮を張り皮として茶筒や小箱に使ったり、曲げ物の綴じ目に用いたりする細工は今日にも続いている。木材としても、緻密で加工しやすく家具材や船材に利用され、「中華には梓を以書を刻む。日本には桜を用ゆ。材堅くして良材なり」(大和本草)といわれているように版木としても広く用いられてきた。
その桜が観賞用の花木として梅の地位を奪った背景には、視覚的な興趣がより重視されるようになった美意識の変化がある。「色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし窓の梅ぞも」(古今―春上三三)と詠われているように、梅は色や形よりも香の面で尊ばれた。それに対して、咲き散る桜の花の動きや色の微妙な変化に一喜一憂するような鑑賞態度が生まれてきたのである。日本国語大辞典第2版には209もの「桜」を冠した熟語が収録されているが、その多くは桜の色を利用して作られたことばである。
さまざまの事思ひ出す桜かな 芭蕉
きのふけふ高根の桜見えにけり 蕪村
したたかに水をうちたる夕ざくら 久保田万太郎
ちるさくら海あをければ海にちる 高屋窓秋
大皿のなまぐさくあり八重桜 波多野爽波
2002-03-25 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



