季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
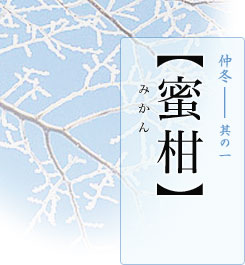
秋は柿、梨、桃などが豊富に出まわり、文字どおり味覚の秋を実感させてくれるが、冬になるとなんといっても蜜柑が主役。色彩がしだいに乏しくなっていく中にあって、鮮やかな蜜柑色がしだいに店頭に増えていくのを見ていると、冬の到来を感じさせるとともに、年の瀬を迎える気持ちも重なって、なんとなくうきうきしてくる。
現在、日本人一人当たり一年間で20キログラムぐらいの蜜柑を食べるといわれている。ジュースなどになる分はこれに入っていないから、もっと消費されていることになる。もちろん果物全体の第一位である。産地では昭和初期まで和歌山県が第一位だったが、その後、静岡県、さらに愛媛県にとってかわり、近年では九州7県だけで全生産量の半分近くを占めている。
品種ではウンシュウミカンが圧倒的に多い。早熟性で、夏は高温多湿で冬は比較的低温な日本の気候風土に適し、千葉県から鹿児島県の、年平均気温15~18度、冬の最低気温-5度以上の地域で栽培されている。ウンシュウミカンは日本を代表する柑橘類として世界中に知られているが、最初に海外に紹介したのはシーボルトで、ついでホールという人が苗木をアメリカに輸出したのが1876年で、これが海外でも栽培されるようになったきっかけである。そのときの英名はサツマ-マンダリンで、これは苗木を船に積みこんだのが薩摩(鹿児島県)だったからである。現在、スペイン、イスラエル、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカでも栽培され、近年は台湾や中国の生産量も伸びている。
ウンシュウミカンのウンシュウは中国の温州で、そこからもたらされたという伝承があるが、実際は江戸初期に浙江省温州付近から持ち帰った種からの偶然実生だろうと推定されている。事実、鹿児島県出水郡長島には、樹齢300年以上のウンシュウミカンの原木が存在している。
ウンシュウミカンをはじめとする最近の蜜柑にはほとんど種がないが、しかし種なし蜜柑が一般に食べられるようになったのは、意外に最近のことで明治以降。江戸の家父長制度のもとでは、種なしは子孫が絶えるということで嫌われたのである。したがってウンシュウよりも種のあるキシュウ(紀州)の方が一般的だった。史的事実ではないとされているが、例の紀伊国屋文左衛門が荒波を乗り越えて江戸へ運んだとされるのはこのキシュウミカンだったわけである。
蜜柑の皮は漢方薬としてもよく使われる。未熟な緑色のものを青皮(じょうひ)、完熟して黄赤色になったのを橘皮(きっぴ)、さらに古くなったのを陳皮(ちんぴ)といって健胃、鎮痛剤として用いられる。またその煎汁は魚やカニによる中毒に効くとされ、お刺身に蜜柑が添えられるのは、この理由によるという。
下積の蜜柑ちひさし年の暮 浪化(ろうか)
酢がとれて蜜柑も年の名残かな 槐本諷竹
埋み置く灰に音を鳴くみかんかな 黒柳召波
足袋の紐結べば蜜柑ころげ落ち 〔柳多留〕
濃かりける日陰日向や蜜柑山 松本たかし
蜜柑山警察船の着きにけり 芝不器男
蜜柑山の中に村あり海もあり 藤後左右
をとめ今たべし蜜柑の香をまとひ 日野草城
死後も日向たのしむ墓か蜜柑山 篠田悌二郎
子の熱のくちびる勁く蜜柑吸う 能村登四郎
夜行過ぎ蜜柑山また里に帰す 堀井春一郎
ここに来て見定めがたしと言ふなかれ
近代のはて蜜柑山照る 坂井修一
2002-12-09 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



