季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
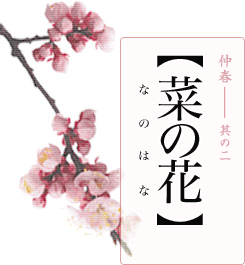
見わたすかぎりの菜の花畑は、春の田園風景の代表的なものの一つ。しかし江戸以前はあまり見られない風景だった。菜の花の種から採る菜種油は、たいへん質のよい灯油になることが知られるようになり、農家の貴重な現金収入源として、その栽培が急速に広まった以降に出現した風景である。
菜の花の「菜」は、副食つまりおかずを表わす「肴(な)」や食用にする魚をあらわす「魚(な)」と語源を同じくし、食用にする草本類を総称する語である。食用にするなら普通は花の咲く前に収穫されるのに、開花するまで育てるのは種から油を採るのが目的だったからである。したがってこの「菜」は「菜」の中でも特に種に油分を多く含む油菜(あぶらな)のことで、食用にする草本はたくさんあるのに特に油菜をさしたのには、こんな背景があった。また油菜を稲作の裏作とすると、稲のできが非常によいということや油を絞ったあとの油かすはよい肥料になったことも、油菜の栽培をさかんにした理由である。
三月の中旬ぐらいから花が咲き始め、五月を過ぎて日差しに暑さを感じる頃から、菜の花は枯れてきて、小さな実がいっぱいにつまった莢(さや)がふくらんでくる。その莢が裂開しないうちに刈り取り、乾かして莢を叩いて実を取り出す。この実は40%以上の油分を含んでいる。これを圧搾法でしぼって採ったのが「白紋油(しらしめゆ)」という菜種油である。
江戸初期は生産力でも経済力でも大阪、京都を中心とする上方が江戸をしのいでいたから、江戸に人が大量に流入し、消費都市として発達すればするほど、その消費物資の供給のため、上方の商業活動も活発化した。菜種油はその代表的なものだった。100樽の油は300俵の米に匹敵する値段がついたというから、その重要性もわかる。その流通は、まず瀬戸内海沿岸の菜種が大阪に集められ、製油され白紋油がつくられた。これに大阪周辺でつくられた白紋油も加わって、多くは海路で江戸に運ばれたのである。
「満地金の如し」(「大和本草」)、「黄なる絹をしけるがごとし」(「農業全書」)と形容される見わたすかぎりの菜の花畑は、単なる新鮮な風景というだけでなく、当時の発達する上方経済を象徴するものとしても人々の目に映っていたことだろう。
菜の花や淀も桂も忘れ水 池西言水
菜の花や鼻のよごれた牛がくる 蝶夢
菜の花や月は東に日は西に 与謝蕪村
菜の花に汐さし上る小川かな 河東碧梧桐
家々や菜の花いろの燈をともし 木下夕爾
馬の首人の首行く菜種かな 五百木飄亭
息せるや菜の花明り片頬に 西東三鬼
電柱のまはり菜の花畑かな 中村裕
ちらばれる耳成山や香具山や
菜の花黄なる春の大和に 佐佐木信綱
いちめんのなのはな/いちめんのなのはな/
いちめんのなのはな/いちめんのなのはな/
いちめんのなのはな/いちめんのなのはな/
いちめんのなのはな/やめるはひるのつき/
いちめんのなのはな 山村暮鳥「風景」
わがわざは成りがたくして/こころざしほろびゆく日を/
近江路に菜の花咲いて/かいつぶり浮き沈むかな 三好達治「わがわざ」
2003-03-10 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



