季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
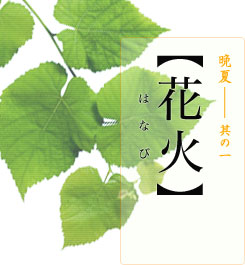
夏を代表する風物詩といえば、花火をあげる人が多いのではないだろうか。歳時記でも夏に入れているものが最近では多い。しかし伝統的には花火は秋のものとされていた。盂蘭盆の景物とされていたからである。ところが新暦になり、お盆が夏の盛りのものと感じられるようになるとともに、納涼と強く結びつき、ますます夏のものとされるようになったのである。
花火の起源をたどることは、火薬の歴史をたどることでもある。花火に欠かせないものは黒色火薬で、その75パーセントは硝石(硝酸カリウム)である。現在でも中国は硝石の世界的な産地だが、火薬も中国で発明されたと考えられている。しかし当初は軍事用の烽火(のろし)に使われる程度だったようだ。それが13世紀頃に非常に発達し、火器にも利用されるようになる。モンゴル軍の使っていたそれが、日本人がはじめて遭遇した火薬である。しかし日本人が本格的に火薬を受容することになったのは、それから270年後、ポルトガル船が鉄砲とともにもたらした火薬との出会いがきっかけになった。
江戸時代初期までは、火薬は重要な戦略物資だったので、市中に出回ることはあまりなかった。平和な時代になり、少しずつそれが出回るようになると、まず線香花火のような小型の花火が作られたようだ。誰がいつ発明したのかはわかっていないが、「手牡丹」という美しい名を付けられ、線香花火はずいぶん古い時代から庶民に愛好されていたようだ。
記録に残っている花火の第一号は、慶長18年(1613)年8月6日、駿府(静岡)の家康のもとに国王ジェームズ一世の国書を携えてきたイギリス人ジョン・セーリスが披露した御前花火である。これは今のような色鮮やかなものではなく、筒に黒色火薬をつめて点火し、噴出する火の粉の様を鑑賞したものだろうと言われている。
万治2(1659)年、大和の篠原村から弥兵衛という男が、葦の管に火薬をつめた花火を売りに江戸に出てきて、これが大いに当たる。この弥兵衛が後の「鍵屋」である。彼は研究熱心だったらしく、その後も大型花火の実験を繰り返し、享保2(1717)年には水神祭りの夜に献上花火を打ち上げ、今日の川開き花火の先鞭をつけた。
しかし瓦屋根の少ない江戸の町では、花火が原因の火災もたびたび起きたので、幾度も花火禁令が出された。それで打ち上げ場所が両国隅田川の大川端に指定され、業者も鍵屋と鍵屋から分家した玉屋などの13軒に限られた。最初にこの両国の大花火が打ち上げられたのは享保18(1733)年5月28日、川開きの日であった。旧暦のこの頃はすでに梅雨に入り、例年、疫病流行の兆しがみえ始める。この前年にも江戸ではコロリ(コレラ)が大流行した。川開きには疫病退散を願う行事という側面もあったのである。
当時の花火は、動きはあっても色は薄いオレンジ色の単色で、光の濃淡と飛び散る火の粉だけの墨絵のようなものだった。今日のような色がつくようになったのは、明治になってマッチの原料である塩素酸カリウムをはじめ、アルミニウム、マグネシウムなどが輸入されるようになってから。テクニカラーの第一号花火は明治22年2月11日の明治憲法記念日に、皇居二重橋前で打ち上げられたものが最初である。
日本の花火は世界最高水準にあるといわれるが、種類も多彩で大きく分けると、「柳」、「蝶」、「牡丹」、「菊」などで、中でも全部で4つの花が開く「三重芯変化菊」は最も精巧なものである。
川舟や花火の夜も花火売り 小林一茶
暗く暑く大群衆と花火待つ 西東三鬼
手花火のこぼす火の色水の色 後藤夜半
2001-07-30 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



