季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
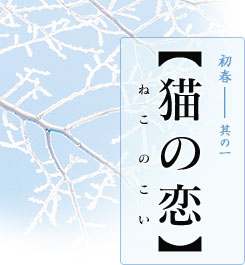
季語というのは、単にその季節に特徴的なものが機械的に選ばれているわけではない。俳句という文芸ジャンルが確立されてくる過程に並行して、選択され、あるいはつくられてきたことばである。だから日常的な用語法とは異なったり、事実とは矛盾することばも多い。「亀鳴く」(春)、「蚯蚓(みみず)鳴く」(秋)という季語があるが、もちろん亀や蚯蚓が鳴くはずがない。鳴くはずのないものが鳴くとしたところに俳句的なおかしみがあり、俳人たちを興がらせてきたのである。
「猫の恋」も同様に、日常的な用法から離れ、俳句的な特徴を強く持った季語である。そもそも「猫の恋」はあるのに「犬の恋」は季語とはされない。犬には相当な不満がたまっていると思うが、おかまいなしである。また繁殖期も一定せず、一月二月三月、五月六月がやや多いといった程度である。かならずしも春ばかりのものではないのである。しかし俳句では春の趣をたたえたものとして早春の季語とするのである。
「猫の恋」は近世初頭には「猫の妻恋」と呼ばれていた。鳴くのは雄の方だからである。その声はやさしい甘え声のようだったり、時に低く長く咽ぶようだったり、脅すようだったり、猛り狂う声、怒り喚く声、泣き叫ぶ声とまったく千変万化。あれほどの声を張り上げているのだから、さぞかしすさまじい修羅場が展開されているのかと、のぞいてみると当人たちは案外、静かににらみ合っているだけだったりする。
その激しくあからさまに性欲をぶつけ合う猫の交尾は、理性によって押さえつけられることの多い人間の恋愛感情を嘆く気持ちを呼び起こし、またある種の諧謔味を帯びる。そのことで、芭蕉以下の正風の俳人たちに好んで詠われた。今日でも俳人たちにとりわけ人気のある季語の一つである。藤原定家に「うらやまし声もをしまずのら猫の心のままに妻こふるかな」(『北条五代記』)という歌があるが、このような卑俗な素材は、雅な和歌、連歌の世界ではあまり取り上げられることはなかった。「うらやまし思ひ切る時猫の恋」という越智越人の句はこの定家の歌をふまえたものである。
両方に髭があるなり猫の妻 小西来山
猫の恋止むとき閨の朧月 松尾芭蕉
麦飯にやつるる恋か猫の妻 〃
京町の猫通ひけり揚屋町 宝井其角
猫の恋初手から鳴いて哀なり 志太野坡
連れて来て飯を喰はする女猫かな 小林一茶
なの花にまぶれて来たり猫の恋 〃
恋猫の皿舐めてすぐ鳴きにゆく 加藤楸邨
恋猫の恋する猫で押し通す 永田耕衣
2002-01-28 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



