季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
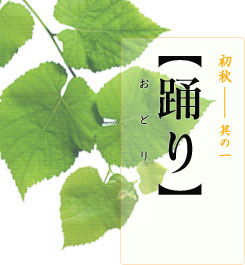
季語の世界においては単に「踊り」というだけで「盆踊り」をさす。つまりさまざまある踊りの中で、お盆に行なわれる踊りがとりわけ日本人の季節感と強く結びついてきたわけである。したがってお盆というものをまず説明しておいた方がいいだろう。
お盆は正しくは「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といって、中国から飛鳥時代に渡ってきた仏教行事で、はじめは宮中や寺院のみで行われていた。盂蘭盆会はお釈迦様の高弟であった目連(もくれん)が地獄に落ちた母親を救い出したという故事に由来し、その日が旧七月十五日だった。もとは先祖供養の意味合いをもつ行事だったのである。その一方で、日本には古来、歳末と夏の終わりの年二回、祖先の霊がその子孫のもとに来臨し、それを迎えてまつることが行なわれてきた。この盂蘭盆会と日本古来の祖霊信仰が習合して、現在のお盆になってきたのである。
しかしそれだけではなく、この旧七月半ばは農作業の面からすると、稲穂が伸び田んぼの手入れも済んで、畑の作物の収穫も一段落して、一休みする時期。この時に親に対して収穫したものなどを贈る習慣が「生御魂(いきみたま)」で、これもちょうどお盆の時に行なわれた。親の長寿、生きていることへの感謝、収穫の報告を兼ねて、贈り物をしたわけである。これがお世話になった人への贈答の習慣「お中元」になっていったともいわれている。つまりお盆は先祖や祖霊を供養したり祭るという死者のための行事というだけでなく、生きていることやものへの感謝を表わす生者のための行事でもあったのである。
盆踊りにはこのようなお盆の成り立ちそのものが含まれているので、きわめて多様である。また、さんさ踊、供養踊、精霊踊、三昧踊、墓踊、燈篭踊、切子踊、盆祭祝儀踊、大宮踊、おしまこ踊、おけさ踊、念仏踊などさまざまな名で全国で行なわれているが、それはその時々に流行した踊りが取り入れられてきたせいでもある。しかしもともとはきわめてシンプルなもので、歌もなかったようだ。日本民謡の分類上に盆踊り唄というのがあるが、歌が盆踊りにつくようになったのは近世のことで、古くは手足の振りや拍子を揃えるための文句があるぐらいだった。青森県七戸地方では「なにやとやれ、なにやとなされの」という文句で踊られているが、この「なんでもやれよ」といった意味の文句で繰り返し踊っているところは全国に比較的多い。
盆踊りのもう一つの要素に歌垣的なものがある。旧暦七月十五夜の満月のもとで、男女が配偶者を求めて歌い踊る古来の習俗も盆踊りに濃厚に入っている。しかしそれが風紀を乱すということで、明治・大正期に再三の厳しい取り締まりがあった。
見知りたる背中どやする躍かな 立花北枝
四五人に月落ちかゝる踊かな 与謝蕪村
あの下手を嫁にと思ふ踊かな 横井也有
てのひらをかへせばすゝむ踊かな 阿波野青畝
月とるごと種まくごとく踊りけり 山口青邨
いとけなき踊を父の裾がくれ 皆吉爽雨
人の世のかなしきうたを踊るなり 長谷川素逝
ひとところ暗きを過ぐる踊の輪 橋本多佳子
踊りゐるうしろ姿のみな暗く 加倉井秋
我を遂に癩の踊の輪に投ず 平畑静塔
またひとり顔なき男あらはれて
暗き踊の輪をひろげゆく 岡野弘彦
2002-08-12 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



