季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
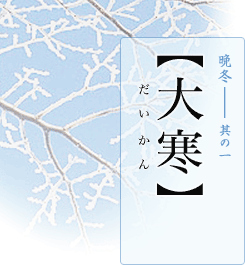
大寒は冬至のほぼ一ヶ月後、1月20日ごろからの15日間。二十四節気では「小寒」(冬至の15日後、1月5日ごろからの15日間)の後にあたり、一年の内で最も寒い時期である。ちなみに「小寒」「大寒」を併せた約一ヶ月間が「寒」であり、1月5日ごろの「寒の入り」から立春の前日の節分(「寒明け」)までの時期を「寒中」「寒の内」と呼ぶ。
「寒の入り」から「寒明け」までの推移を、俳句を鑑賞しながらみてみよう。
晴天も猶つめたしや寒の入 杉風
うす壁にづんづと寒が入りにけり 一茶
きびきびと万物寒に入りにけり 富安風生
黒松の幹の粗さや寒に入る 森澄雄
「寒の入り」の句には、さえざえとした寒気に向かう緊張感が漂うものが多い。
小寒や枯草に舞ふうすほこり 長谷川春草
小寒のさゞなみ立てて木場の川 山田土偶
「小寒の氷が大寒に解ける」という言葉があり、年によっては小寒の方が大寒より寒さが厳しいことも少なくない。春の訪れがかすかに感じられる大寒に比べて、小寒の時期は「寒の内」の最盛期なのである。
大寒の大々(だいだい)とした月よかな 一茶
大寒の埃の如く人死ぬる 高濱虚子
大寒やしづかにけむる茶碗蒸 日野草城
大寒の月光させる厨(くりや)かな 金尾梅の門
大寒の一戸もかくれなき故郷 飯田龍太
大寒は寒さの極まる時期でありつつ、春の予感がじわじわと迫ってくる時期でもある。梅が咲き始め、すこしずつ日が長くなってくる。「大寒」という字面や音が、のびのびとしたスケールの大きさを感じさせることもあり、大寒の句には空間の広さや重厚な厚み、どことなくほっとさせる暖かさを内包した作品が多いようだ。
蜂の巣も投じて焚火寒明くる 皆吉爽雨
或る家で猫に慕はれ寒明くる 秋元不死男
寒明けの波止場に磨く旅の靴 沢木欣一
寒明や横に坐りて妻の膝 草間時彦
「寒明け」は春の季語となる。時期的には立春と同じだが、長い「寒」の季節の終わりを直接的に喜ぶ感情がはっきりと出た作品が多い。
2003-01-27 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



