季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
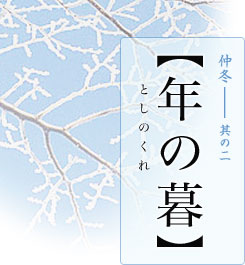
一年を締めくくる期間を漠然と「年の暮」というが、一般的には十二月の中旬ころから、正月の準備を始める家が多いので、そのころから年の暮の実感が深まってくる。実際にこまごまとやらなければならないことも多いのだが、そうでなくても、なんとなく気がせいて落ち着かない気持ちになるのは、日本人以外にはあまりないことのようだ。
ひとつには日本が稲作農耕を中心とした社会だったせいかもしれない。「年」という字は稲魂が宿る「禾(か)」を被って舞う人を表わし、豊穣を祈る農耕儀礼を意味した。「とし」も、もとはといえば穀物が一回実る期間が一年に相当するところから、五穀、特に稲、またはその収穫や作柄をいうことばだった。「御年神(みとしのかみ)」といえば稲を神格化したものである。農耕のサイクルで日々の生活が営まれていたから、収穫が終わり、次の作付けに備えるこの期間は、農閑期とはいえやることも多く、それなりに気ぜわしい時期なのである。その習慣や記憶が現代人にも残っているのかもしれない。
「年の暮れはてて、人ごとにいそぎあへる頃ぞ、またなくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の、寒けくすめる廿日あまりのそらこそ、心細きものなれ」という『徒然草』第十九段の記述は、年末の慌しさを印象的に伝えているが、江戸時代、年の暮といえばまず「煤払い」が大事な行事だった。現在では暮れもおしせまった二十七、二十八日から大晦日にかけて行うところが多いようだが、江戸の寛永以降は十三日に行うのが恒例になっていた。これは江戸城内ではこの日が煤払いの日と決められていたからである。江戸市中もそれにならったのである。当時の燃料は炭や薪なわけだから、一年分の煤の量は相当なもので、この日は江戸中が煤だらけといった様相を呈した。しかし楽しい年中行事といった側面もあって、案外、遊び半分で楽しまれてもいたようだ。特に商店では終わると胴上げをしたり、祝儀酒が振舞われたりした。この日は早寝というのが建前になっていたが、手代や丁稚の中にはこっそり寝床を抜け出し遊びに出かけるというのも多く、また主人もそれを大目にみたようだ。
煤払いのあとは「餅つき」ということになる。こちらの日は別に決まっていず、二十日から二十七日ころの間に行なわれた(二十九日にはつかなかった)。したがって「黒く白く二度よごれて春となり」と川柳がいうのが実感だったのである。
しかし江戸の庶民にとって、年を越すには最後に大きな関門があった。かけ取りや借金取りである。当時は盆暮勘定で特に暮れの勘定は大事だったから、最後の最後まで、つまり大晦日まで攻防が繰り広げられた。これは落語などの恰好の材料にもなった。「武蔵野の蛍合戦大晦日」という川柳があるが、借金の金を工面しようとする人と通い帳にある代金をなんとしても払ってもらおうとする人が、夜になっても提灯を持ち、さかんに行き交うさまを蛍合戦に見立てたわけである。しかしめでたく仕払いが済めば「帳面に霞を引くと春になる」。すがすがしく元日の朝を迎えることができるというわけである。
惜めども寝たら起たら春であろ 上島鬼貫
白昼に雉拾ひけり年のくれ 池西言水
分別の底たゝきけり年の暮 松尾芭蕉
うつくしや年暮れきりし夜の空 小林一茶
下駄買うて箪笥の上や年の暮 永井荷風
ラゝラゝと青年うたひ年暮るる 山口青邨
玻璃窓を鳥ゆがみゆく年の暮 西東三鬼
煤はきは己が棚つる大工かな 松尾芭蕉
煤はきや旭に向ふ鼻の穴 小林一茶
なれなれて年の暮とも驚かぬ
老いのはてこそあはれなりけれ 香川景樹
歳末の風に吹かれて木の葉二
立ちあがりつつ隠ろひゆけり 山下陸奥
2002-12-24 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



