季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
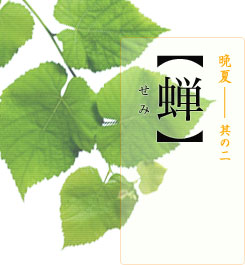
季語(季題)には本意というものがかならずあって、それを俳句の中に使う場合は、あらかじめ決まっている本意の範囲内の意味でしか、その季語を使ってはいけないというのが伝統的な考え方。たとえば「春雨」はどんなに強く降っていようが、しとしといつまでも降り続くように詠まなければならない。「古池や蛙飛びこむ水の音」(芭蕉)が革新的な俳句とされたのは、蛙とくればその鳴き声を詠むのが約束だったのに、飛びこんだ水の音をもってきたからである。
蝉の本意もかつての蛙と同じく鳴き声、蝉の声である。左右の大脳半球がそれぞれ言語と音楽に対応する機能を持つとする説によれば、日本人は虫や動物の鳴き声を左半球の言語脳で聞く珍しい民族らしい。ところが虫の声でも蝉とキリギリスだけは例外で、言語半球の優位性は認められないという。つまり日本人にとって蝉の声は、ほかの虫の声にくらべより純粋な音として聞いているということになる。音としての独立性が高いのである。
六月終わりの梅雨明け頃からにいにい蝉が鳴き始める。ジーッジーッと鳴き、チッチッと鳴きおさめる。芭蕉が山形の立石寺で詠んだ「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」の蝉だといわれている。ついで油で揚げるようなジージーとやかましい声の油蝉。みんみん蝉は別名、深山蝉。ミーンミーンと高い声で繰り返し鳴く。いちばん大きな声でやかましいのは関西に多いくま蝉で、シャーシャーといっせいに鳴いている森の中などにいるとたまらない。七月に入れば場所によって蜩(ひぐらし)がカナカナと涼しい美しい声で鳴きはじめる。続いて八月に入り秋風が立ちはじめる頃には、つくつく法師(寒蝉)。ツクツクホーシ、ツクツクホーシ、オーシーツクツク、オーシーツクツク、そしてジーと鳴きおさめる。蜩もつくつく法師も蝉といいいながら、その鳴き声の感じもあって、秋のものとされている。
蝉は命の短さの代名詞になるぐらいだが、実際の成虫期間は10日から20日に及ぶ。しかし幼虫の期間はきわめて長く、数年から17年間もの地下生活を送る。それから、もちろん鳴くのは雄の方で、雌は唖蝉(おしぜみ)と呼ばれる。「蝉は幸いなるかな、その妻は鳴かざればなり」(クセナルコス)
蝉に関する季語で忘れてはならないのは「空蝉(うつせみ)」。つまり蝉のぬけがらである。長い時間をかけて、地中で幼虫から蛹(さなぎ)になり、地を出て木に登り、背中から割れてその皮を脱ぐ。その皮を蝉の殻とか空蝉とかいうのである。空蝉の「うつ」は「うつろ」「うつわ」の「うつ」で、中が空っぽの意味だが、もともとの「うつせみ」は「この世(の人)」という意味で「万葉集」などでは使われていた。しかしそれに「空蝉」「虚蝉」といった字を当てたために、文字どおりの意味を生んでしまい、しだいにはかないもののたとえになっていったと思われる。
やがて死ぬけしきは見えず蝉の声 松尾芭蕉
蝉の殻流れて山を離れゆく 三橋敏雄
空蝉の両眼濡れて在りしかな 河原枇杷男
2001-08-13 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



