季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
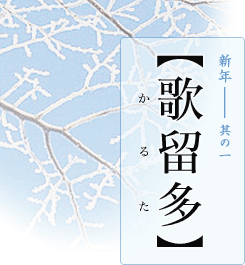
お正月には人が集まることが多く、冬季でもあることから、羽子板などは例外として、室内での遊戯がさかんである。カルタ遊びは双六遊びとともに、お正月の室内遊戯の代表といってよいだろう。生活様式の変化によって、かつてほどはさかんに遊ばれてないとはいえ、学習用としてや美術品としても、その命脈の絶えることはなさそうだ。
しかし季語としてのカルタが定着するのは案外に新しく、江戸中期以降である。寛永期の俳書『毛吹草』でも季節は定まっていないし、延宝期の『色道大鏡』では一座のさびしい折りに随時興ずるものとしてあげているにすぎない。それがしだいに庶民の間に浸透していって、季語としても定着し、また博打的なものも出現して、幕府に禁止されるほどまでになるのである。明治に入ってもたいへんに流行し、尾崎紅葉の『金色夜叉』で、有名なお宮と富山の出会いのシーンはカルタ会である。
ひとくちにカルタといってもさまざまあるが、そのルーツには南蛮渡来の南蛮カルタと貝覆(かいおおい)に発した歌カルタの系統があり、後者が前者の影響を受けながら多種多様なカルタがつくられてきた。カルタの語源はカルテ、カードと同源のCARTAで、これがポルトガル語、イスパニア語から入ってきたものである。ちなみに始めから終わりまで、最上のものから最低のものまでをさす「ピンからキリまで」ということばの「ピン」はpINTA(点、1)、「キリ」はCRUZ(十字架、10)というカルタの札の数やサイコロの目の数を表わす西欧語からきたものである。
南蛮渡来のカルタがどんなものだったのか現存しないのでわからないが、それを模した天正カルタがわずかに一枚だけ残っている。当時の文献から推定されるのは、ESpADA(剣)、pAU(棍棒)、COpO(コップ)、OURO(金貨)の四種からなり、一種ごとに1~9までの数札、10の法師、11の騎士、12の庶人があり、計48枚ということになる。つまり現在のトランプと原理的には同じものである。これを使った博打が江戸初期、熱狂的に流行したため、度重なる禁令が出される。その禁令をのがれるためにつくられたのがウンスンカルタである。布袋、福禄寿、恵比寿、大黒、達磨などを加え、札も75枚に増えるが、遊び方が複雑になっただけで、原理は天正カルタと同じである。これがさらに天正カルタを上まわる爆発的な人気を集めたため、またまた禁令にあう。それでさらに絵柄を日本風にしたのが花カルタ(花札)である。
貝覆は360個の蛤の貝殻をそれぞれ二つに分け、一方の360個を地貝と称して席上に並べ、それに合う貝をより多く見つけた方を勝ちとするというものである。この貝の内側に絵や歌を書くようになり、さらにウンスンカルタの影響で貝が紙製になって歌カルタが生まれる。歌カルタの中では小倉百人一首が最も広く用いられ、現在にも続いているが、それ以外にもいろはカルタをはじめとして、種々の歌カルタがあった。源氏物語や伊勢物語の歌をもとにしたもの、漢詩や俳句をもとにしたもの、あるいは格言、諺、教訓をもとにしたものなど、実に多様な歌カルタの世界が花開いていたのである。
鶯やささやひてとる歌がるた 上松木導
座を挙げて恋ほのめくや歌かるた 高浜虚子
座について加留多上手のさりげ無く 大谷繞石
胼の手も交りて歌留多賑はへり 杉田久女
歌加留多人づてならで友の来し 伊藤松宇
歌がるた眼鏡ばかりや西の組 羅蘇山人
読む歌留多月にあがりぬ路地の奥 原 石鼎
封切れば溢れんとするかるたかな 松藤夏山
敵のかるた一つの歌がわが眼牽く 橋本多佳子
2003-01-15 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



