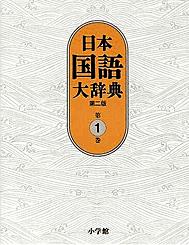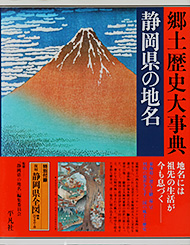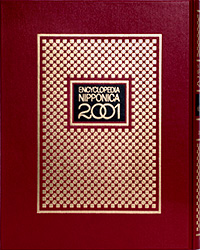ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。
国史大辞典 episode.4
『国史大辞典』の第1巻が上梓されたのは、昭和54(1979)年。編纂スタートからすでに14年の歳月が経過していた。長い助走期間。当然そこには、社内外の批判も集まった。「発売できないかもしれない」──この刊行危機をいったいどう乗り越えたのか。吉川弘文館の前田求恭社長にお話をうかがう4回目。
懐に辞表をしのばせて…委員会ごと身売りの危機

──第1巻が出るまで10年以上かかる。これは当時としても、非常に時間がかかっています。批判はなかったのですか?
もちろん、社内外から多くの批判が集まりました。『国史大辞典』は、当時の吉川圭三社長が「委員会組織で作る!」と決めたことで、社内のベテラン編集者たちを関与させない結果となりました。事務局にも、発足当初は、編集のイロハも知らない新入社員の私が1人いただけ。あとは新進の先生方で占められていました。ほかの社員から見れば「『国史大辞典』の連中は何をしてるんだ!」ということになります。成果物を出していないから、お金は使うばかりで、入ってこない。それでも圭三社長が、「『国史大辞典』は、事務局長の皆川完一先生と前田君に任せておけばいいんだ」と社内の批判を突っぱねてくれた。そのお陰でなんとかやっていくことができたのでしょう。もし私がベテラン編集者の立場だったら、同じように不安や不満を感じると思います。しかし社内の人は納得させることができても、金銭的な部分は、大問題として残りました。編集委員会ごと身売り、という話すらあったのです。
――発行直前の『国史大辞典』を売ってしまう?
それほど逼迫していました。なにせ10年経っても本が出ないんですから(笑)。原稿依頼自体は、昭和45年からスタートしたのですが、圭三社長は「原稿料は400字詰め1枚3000円、原稿受領後2か月以内にお支払いします」と執筆要項にうたってしまったのです。昭和40年の大卒初任給が2万3000円で、その当時の3000円ですから破格です。刊行後の支払いでしたら、売り上げが見込めますが、これだと刊行前に払わなければなりません。それが何万項目にも及ぶのですから推して知るべし、です。社長は真剣に身売りを考えていました。当然、委員会は大反対です。このままではせっかくの大事業が頓挫する。それは日本の歴史学を後退させてしまうんじゃないか、そんな危機感さえありました。私はひとり嘆願書を作り、社長の自宅に乗り込んだんです。昭和50年ころのことだったでしょうか。私は懐に、辞表をしのばせていました。どちらにせよ、責任を取って辞めざるを得ないと思っていたのです。社長は踏ん張ってくださり、ぎりぎりのところで危機は脱しました。お陰で事務局は何度も銀行の調査を受け、私はお金を借りるための計画表の提出を幾度も迫られましたが(笑)。
「辞典は鑑だ」という思いをいつも胸に抱いて
――編纂開始から5年後の昭和45年、執筆依頼がスタートします。
しかし、全部の原稿をいっせいに依頼する、ということはしませんでした。その時点の最高水準の先生方に対し、まず第1巻・2巻に入る、「あ~お」までの項目を依頼しました。一度目にある程度の分量を依頼して、それを私ども事務局と編集委員が拝見します。お忙しい先生たちですから、中には気乗りのしない方もいましたし、弟子たちに書かせてきた方もいました。そういう方には次回の依頼からご遠慮いただきました。原稿のレベルを一定水準に保つようにしたかったからです。
――執筆者との間で原稿の修正のやりとりも何度もされたんですか。
特注の黄色い封筒を作りまして、先生の原稿に赤字を入れ、質問を添えて、お送りしました。社内からは「その道の専門家の書いた原稿に、素人の編集者がケチをつけるのか」と批判されましたし、執筆者の先生からも相当怒られました。「前田君から送られてくる黄色の封筒は、恐怖の封筒だね」と言われたことも何度もありました(笑)。それでも、吉川圭三社長以下、スタッフ全員「辞典は鑑だ」という意識がありました。いい辞典を作りたい。その思いを前に、少々の批判は苦になりませんでした。


著者からの原稿。現在もまだ氏名ごとにきれいに保管されている。当時は金庫に原稿を入れていた。事務局、校閲用にコピーを2通とることが決まりだった。

著者から恐れられた、"恐怖の黄色い封筒"。中身は編集委員会からの厳しい質問状。名の知れた執筆者といえども、容赦しなかった。
 前田求恭(まえだ・もとやす)
前田求恭(まえだ・もとやす)
1942年生まれ。株式会社吉川弘文館代表取締役社長。國學院大学文学部史学科卒業。1965年、同社に入社すると同時に、『国史大辞典』の事務局スタッフとして編集者人生をスタート。97年の完成まで『国史大辞典』の制作ひとすじ。その後『日本の時代史』(全30巻)などを手掛けた。2006年より現職。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。
日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。
(2024年5月時点)