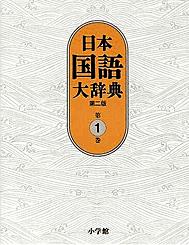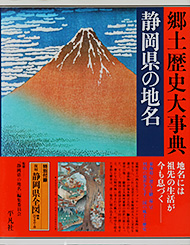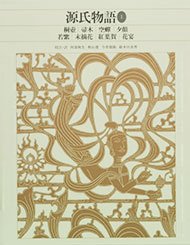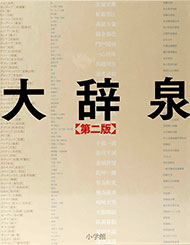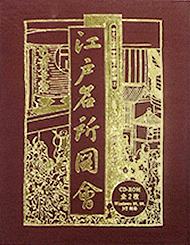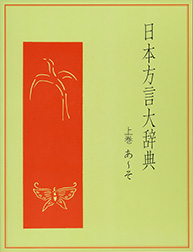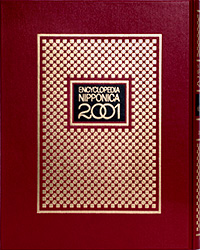ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。
文庫クセジュ episode.4
ジャパンナレッジ後のクセジュのカタチ

──『文庫クセジュ』がネットから読めるようになると、何か変化は起こるでしょうか?
芝山「媒体は違っても、中身が変わるわけではありません。“知”の価値を信じていたい」
中川「1751年の『百科全書』が、手に取りやすい『クセジュ』というカタチに変化し、それが今度はネットになった。カタチは変われども、その志や、知を蓄積することの有益さは、決して変わらないと思うんです」
和久田「デジタルデータ化され、ジャパンナレッジに搭載されることで、検索の利便性が高まりました。他の辞書などとの串刺し検索も可能になりますから、より知の幅は広がるでしょうね」
中川「これまでクセジュを手に取らなかった人たちにも、これをきっかけにより広く知ってもらえるとよいですね」
和久田「私は、学ぶということは、伽藍(がらん)をつくっていくことだと思っているんです。人それぞれのカタチ、大きさがあっていい。“マイ伽藍”を持つことが、その人の深みに繋がるんじゃないでしょうか」
浦田「私は、この4月からクセジュの新しい担当になりますが、個人的には、新しい知識に触れることが刺激的です。前世がフランス人かと思うぐらい、フランスの空気感が好きなので“フランス人のものの見方”という点でも興味があります。だから皆さんにも、ジャパンナレッジを通して、フランスの知の空気を存分に味わっていただきたいですね」
それぞれのおススメ「クセジュ」とは?

──ジャパンナレッジには「文庫クセジュ ベストセレクション」として、354冊が掲載されます。ぜひ、オススメの本を紹介してください。
芝山「記念すべきクセジュの800点目が『ダンテ』なんです。社内の中で最もイタリアに関心があるという理由で、担当が回ってきたのですが、私が唯一担当したクセジュだということもあって、いちばん記憶に残っています。手前味噌になりますが、当時のイタリアの様子やダンテの生涯が、立体的に浮かび上がってきます」
和久田「“知の巨人”たちに、ぜひ触れて欲しいですね。例えば、マルクスの『資本論』を読破することは難しいけれど、その思想の骨格は、クセジュで知ることができる。リズム分析の理論家としても知られるアンリ・ルフェーヴルが書いた『改訳 マルクス主義』は、中でもわかりやすい一冊です。同じ理由で、『ミシェル・フーコー』や『ベルクソン』(J=L.ヴィエイヤール=バロン著/上村博訳)も入門書として最適です」
中川「それほど肩肘張らずに読むことができて、かつ何回も読み直したい。そんな観点で推薦するなら、『フランスの温泉リゾート』や『古代ローマの日常生活』。“知のガイドブック”という感じで、興味深く読むことができます。美食について書かれた『ガストロノミ』、『悪魔の文化史』や『キリスト教シンボル事典』も、一読者として面白かったですね。地誌もののなかでも『カタルーニャの歴史と文化』のように、類書がほとんどないものが読めるのもクセジュの特色かもしれません」
浦田「4月に、私が担当する『プラトンの哲学』(ジャン=フランソワ マテイ著/三浦要訳)という新刊が出るんですが、ぜひ、すでに出ている『プラトン』と読み比べていただきたいですね。いったいどんな新説がプラスされたのか、そのアップデートの仕方が面白いかもしれません」
芝山「2015年、白水社は100周年を迎えるんですが、今の発行ペースだと、ちょうどこの年にクセジュ1000点目が出るんです。ますます、伝統の重さがのしかかってきますね(笑)」
浦田「新担当として、本当に荷が重いですが、クセジュの知の伝統を継続させなければ、と思っています。“クセジュ10年”になるまでがんばれるかどうか、わかりませんが(笑)」
和久田「クセジュの仕事も、そして中身も、常に刺激的であることは、元担当者として保障しますよ」
クセジュ担当者おススメの10冊
| 推薦者 | タイトル・著者・訳者 | ジャンル |
 芝山 |
『ダンテ』 (マリーナ・マリエッティ著/藤谷道夫訳) |
語学・文学 |
 和久田 |
『改訳 マルクス主義』 (アンリ・ルフェーヴル著/竹内良知訳) |
哲学・心理学・宗教 |
| 『ミシェル・フーコー』 (フレデリック・グロ著/露崎俊和訳) |
哲学・心理学・宗教 | |
 中川 |
『フランスの温泉リゾート』 (フィリップ・ランジュニュー=ヴィヤール著/成沢広幸訳) |
歴史・地理・民族(俗)学 |
| 『ガストロノミ――美食のための知識と知恵』 (ジャン・ヴィトー著/佐原秋生訳) |
芸術・趣味 | |
| 『古代ローマの日常生活』 (ピエール・グリマル著/北野徹訳) |
歴史・地理・民族(俗)学 | |
| 『キリスト教シンボル事典』 (ミシェル・フイエ著/武藤剛史訳) |
哲学・心理学・宗教 | |
| 『悪魔の文化史』 (ジョルジュ・ミノワ著/平野隆文訳) |
歴史・地理・民族(俗)学 | |
| 『カタルーニャの歴史と文化』 (ミシェル・ジンマーマン、マリクレール・ジンマーマン著/田澤耕訳) |
歴史・地理・民族(俗)学 | |
 浦田 |
『プラトン』 (ジャン・ブラン著/戸塚七郎訳) |
哲学・心理学・宗教 |

「文庫クセジュ ベストセレクション」の「改訳 マルクス主義」より。可読性を高めるために、1ページは400~800文字を表示。作品名および著者名、訳者名だけでなく、ジャンルも一目でわかる。画面に表示されている本文の位置がリストでわかる「パンくずリスト」、前後だけでなく、巻頭巻末などにジャンプできる「ページナビゲーション」がある。そして右側の目次はクリックすれば、そのページにアクセスすることができる。
くわしくはこちら
https://japanknowledge.com/contents/
quesaisje/
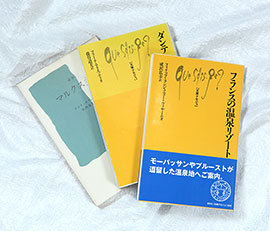
左から和久田さんおススメの『改訳 マルクス主義』、芝山さんおススメの『ダンテ』、中川さんおススメの『フランスの温泉リゾート』。

2012年春に刊行される、文庫クセジュの原本。(写真左から)文庫クセジュでは『プラトンの哲学─神話とロゴスの饗宴』(4月13日予定)、『コンスタンティヌス─その生涯と治世』(発売中)、『オートクチュール─パリモードの歴史』(5月予定)というタイトルで発売。
 芝山 博(しばやま・ひろし)
芝山 博(しばやま・ひろし)
1948年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。白水社常務取締役編集担当。72年白水社入社。営業部を経て編集部へ。編集部では主にイタリア関係の書籍を担当。文庫クセジュでは800点目の『ダンテ』を編集。
 和久田頼男(わくた・としお)
和久田頼男(わくた・としお)
1968年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。白水社に入社後、演劇雑誌と文庫クセジュの編集長を歴任。哲学・思想の古典をアーカイブしてゆくシリーズ「白水iクラシックス」も手がけている。クセジュ時代、現在の黄色の表紙にデザインを一新した。
 中川すみ(なかがわ・すみ)
中川すみ(なかがわ・すみ)
1960年、東京都生まれ。学習院大学フランス文学科卒業。絵本の翻訳の仕事などを経て、2003年から文庫クセジュ編集部へ。2006年、900点目の刊行を見届ける。この春、「クセジュ10年」(苦節10年)に1年届かない9年で卒業。
 浦田滋子(うらた・しげこ)
浦田滋子(うらた・しげこ)
京都府出身。大阪外国語大学フランス語学科卒業。前職はNHKで国際放送局フランス語放送や、NHKラジオフランス語講座の収録、編集に携わる。2012年春から、中川さんに代わり、文庫クセジュの新編集担当となる。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。
日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。
(2024年5月時点)