サンプルページ一覧
オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」に掲載されているコンテンツの項目本文のサンプル一覧です。
※更新等により実際の内容と一部異なる場合があります。
※更新等により実際の内容と一部異なる場合があります。
ジャパンナレッジは日本最大級のオンライン辞書・事典サービスです。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。

アラビアン・ナイト(東洋文庫)
東洋文庫71 前嶋信次訳 中世ペルシア語からアラビア語に訳された説話をもとに,各地の説話を糾合して16世紀のカイロで編まれたアラビア語文学の傑作。アラビア語原典からの完訳は,重訳によって生じた従来の歪んだイスラム観を正す

和漢三才図会(東洋文庫)
東洋文庫447 寺島良安 島田勇雄・竹島淳夫・樋口元巳訳注
江戸中期,大坂の医師寺島良安が中国・明の王圻(おうき)の『三才図会』にならって編んだ,わが国初の図入り百科事典の口語訳。天文,地理から動植物,人事まで,類書を博引傍証して解説する
江戸中期,大坂の医師寺島良安が中国・明の王圻(おうき)の『三才図会』にならって編んだ,わが国初の図入り百科事典の口語訳。天文,地理から動植物,人事まで,類書を博引傍証して解説する

捜神記(東洋文庫・日本大百科全書・集英社世界文学大事典)
東洋文庫10 干宝 竹田晃訳 作者は4世紀半ば,東晋の歴史家で,本書は民間伝説,名士の逸話などを古い書物から抄録したもの。志怪小説とよばれる怪異の記録中もっとも叙述にすぐれ,中国小説の祖とされる。本邦初の全訳。目次 表紙(扉)捜神記原序 巻一

唐代伝奇集(東洋文庫)
東洋文庫2 前野直彬編訳 3~6世紀の六朝時代に伝えられたインド的空想が中国で見事に花開き,妖しい美しさに読者をひき入れるのが唐代の小説「伝奇」である。広い資料のなかから選びぬかれた珠玉の作品111編のうち,第1巻は,比較的長い物語34話

甲子夜話(東洋文庫・世界大百科事典)
東洋文庫306 上は将軍大名の逸話から,下は狐狸妖怪の奇聞まで,ありとあらゆる話柄を記した江戸時代随筆集の白眉。表題は,文政4年(1821),静山62歳の11月甲子の夜に起筆されたことにちなむ。第1巻は,巻一から巻十九まで
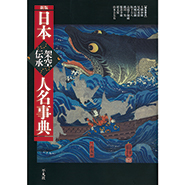
空海(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典)
774‐835(宝亀5‐承和2)弘法大師、俗に「お大師さん」と略称する。平安時代初期の僧で日本真言密教の大成者。真言宗の開祖。讃岐国(香川県)多度郡弘田郷に生まれた。生誕の月日は不明であるが、後に不空三蔵(七〇五‐七七四)の生れかわりとする
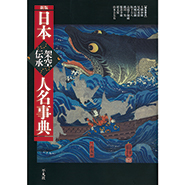
最澄(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典)
767‐822(神護景雲1‐弘仁13)伝教大師。平安初期の僧侶。天台宗の開祖。三津首百枝の子という。幼名は広野。俗姓は三津氏で、帰化人の子といわれる。近江国滋賀郡古市郷(現、滋賀県大津市)の生れ。七七八年(宝亀九)一二歳で近江国分寺の大国師行表
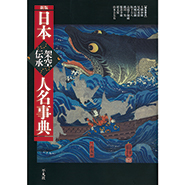
坂上田村麻呂(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
758‐811(天平宝字2‐弘仁2)平安初頭の武将。犬養の孫。苅田麻呂の子。坂上氏は応神朝に渡来したという阿知使主(あちのおみ)を祖先とし大和国高市郡に蟠踞(ばんきょ)した倭(東)漢(やまとのあや)氏の一族で、武術に秀でていた。田村麻呂も
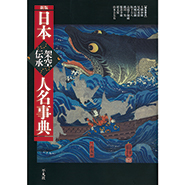
道鏡(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
?‐772(宝亀3)奈良後期の政治家、僧侶。俗姓弓削連。河内国若江郡(現、八尾市)の人。出自に天智天皇皇子志貴(施基)皇子の王子説と物部守屋子孫説の二説がある。前者は『七大寺年表』『本朝皇胤紹運録』等時代の下る書に見える
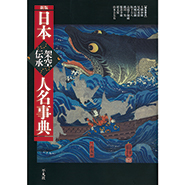
鑑真(新版 日本架空伝承人名事典・世界大百科事典)
688‐763 中国、唐代の高僧。唐の揚州江陽県の生まれで、揚州の大雲寺で出家し、二〇歳で長安や洛陽の高僧から戒律関係の教理や、律宗・天台宗の教義を学んだ。とりわけ僧尼が遵守すべき戒律を研究し、南山律宗の継承者として日夜活動
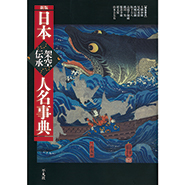
行基(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典)
668‐749(天智7‐天平勝宝1)奈良時代の僧。父は高志才智(こしのさいち)、母は蜂田古爾比売(はちたのこにひめ)。高志氏は百済系渡来人の書(文)(ふみ)氏の分派。行基は河内国(大阪府)大鳥郡の母方の家で生まれた
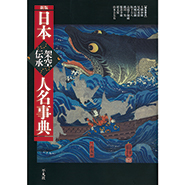
藤原鎌足(新版 日本架空伝承人名事典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
614‐669(推古22‐天智8)大化改新の功臣で藤原氏の始祖。もと中臣連(なかとみのむらじ)鎌足。父は弥気(みけ)(御食子(みけこ)、御食足(みけたり)とも)といい、推古・舒明朝に仕えた神官で、地位は大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)
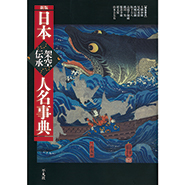
聖徳太子(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典)
?‐622(推古30)六世紀末~七世紀前半の政治家、仏教文化推進者。用明天皇の皇子で母は穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后(欽明天皇皇女)。生年は『上宮聖徳法王帝説』に甲午年(五七四)とあるが確かでない。幼名を厩戸豊聡耳
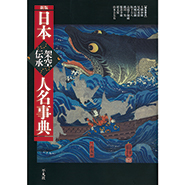
日本武尊(新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
『古事記』『日本書紀』『風土記』などに伝えられる英雄伝説の主人公。記では倭建命と記す。景行天皇の第三皇子で、母は播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおおいらつめ)とされ、幼名に小碓(おうす)命、倭男具那(やまとおぐな)王がある。
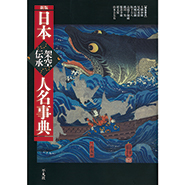
卑弥呼(新版 日本架空伝承人名事典・世界大百科事典)
二世紀末から三世紀前半にかけて、倭国すなわち当時の日本を統治したとされる邪馬台国の女王。しかし、彼女は日本にまだ文字がなかった時代の人物であり、日本の史料にはいっさい登場しない。忽然とその姿を登場させるのは、三世紀に中国で成立した

太上天皇(国史大辞典・日本国語大辞典)
譲位した天皇の称。「だいじょうてんのう」とも訓む。略して上皇あるいは太皇ともいい、また御在所を意味する院の称も用いられ、さらにその御在所を神仙の居所に擬して仙院・仙洞・藐姑射山(はこやのやま)・茨山(しざん)などとも称された。

上皇(日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
譲位した天皇の尊称。正式には太上(だいじょう)天皇と称する。中国の太上皇(たいじょうこう)、太上皇帝の称に始まり、太上は最上または至上の意。日本では697年(文武天皇1)譲位した持統(じとう)天皇が初めて太上天皇と称し、大宝令(たいほうりょう)

昭和天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一九〇一 - 八九 一九二六―八九在位。明治三十四年(一九〇一)四月二十九日午後十時十分、東宮御所に生誕。皇太子明宮嘉仁親王(のちの大正天皇)と皇太子妃節子(のちの貞明皇后)の第一皇子。五月五日明治天皇より裕仁(ひろひと)と命名され

大正天皇(国史大辞典)
一八七九 - 一九二六 一九一二―二六在位。明治十二年(一八七九)八月三十一日午前八時十二分、東京青山御所内御産所にて生誕。明治天皇第三皇子、生母権典侍柳原愛子。九月六日、嘉仁(よしひと)と命名、明宮(はるのみや)と称した

明治天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一八五二 - 一九一二 一八六七―一九一二在位。嘉永五年(一八五二)九月二十二日、孝明天皇の第二皇子として京都石薬師門内の権大納言中山忠能の邸に生まれる。生母は忠能の娘典侍中山慶子。幼称は祐宮(さちのみや)。幼少時は中山邸で起居したが

孝明天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一八三一 - 六六 一八四六―六六在位。天保二年(一八三一)六月十四日仁孝天皇の第四皇子として誕生。母は贈左大臣正親町実光の女雅子(新待賢門院)。諱は統仁(おさひと)、幼称は煕(ひろ)宮という。天保六年六月儲君治定、同年九月親王宣下

桃園天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一七四一 - 六二 一七四七―六二在位。諱は遐仁(とおひと)、幼称ははじめ八穂宮(やほのみや)といい、のちに茶地宮(さちのみや)と改称。桜町天皇の第一皇子として寛保元年(一七四一)二月二十九日誕生。母は開明門院(権大納言姉小路実武の女定子)

霊元天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一六五四 - 一七三二 一六六三―八七在位。諱は識仁(さとひと)、幼称は高貴宮(あてのみや)。後水尾天皇の第十九皇子として承応三年(一六五四)五月二十五日誕生。母は新広義門院(贈左大臣園基音の女国子)。誕生の年、後光明天皇の養子と定められ

後水尾天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一五九六 - 一六八〇 一六一一―二九在位。慶長元年(一五九六)六月四日後陽成天皇の第三皇子として誕生。母は関白近衛前久の女前子(中和門院)。諱は政仁(ことひと、初訓「ただひと」)。同五年十二月二十一日親王宣下、同十六年三月二十七日

後陽成天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一五七一 - 一六一七 一五八六―一六一一在位。元亀二年(一五七一)十二月十五日正親町天皇の皇子誠仁親王(陽光太上天皇)の第一王子として誕生。母は贈左大臣勧修寺晴右の女晴子(新上東門院)。初名和仁(かずひと)、慶長三年(一五九八)十二月

正親町天皇(国史大辞典)
一五一七 - 九三 一五五七―八六在位。諱は方仁(みちひと)。永正十四年(一五一七)五月二十九日生まる。後奈良天皇の第二皇子、母は参議万里小路賢房の女贈皇太后栄子(吉徳門院)である。天文二年(一五三三)十二月親王宣下および元服の儀を挙げ

後奈良天皇(国史大辞典)
一四九六 - 一五五七 一五二六―五七在位。明応五年(一四九六)十二月二十三日後柏原天皇の第二皇子として権中納言勧修寺政顕第において誕生。母は豊楽門院藤原藤子(贈左大臣勧修寺教秀の女)。諱は知仁(ともひと)。永正九年(一五一二)四月八日親王宣下

後花園天皇(国史大辞典)
一四一九 - 七〇 一四二八―六四在位。名、彦仁(ひこひと)。応永二十六年(一四一九)六月十八日生まれる。父は、早世した兄治仁(はるひと)王のあとを継いで伏見宮第三代となった貞成(さだふさ)親王(後崇光院)。母は、右近衛少将庭田経有の娘幸子

後小松天皇(国史大辞典・日本大百科全書)
一三七七 - 一四三三 一三八二―一四一二在位。名、幹仁(もとひと)。永和三年(一三七七)六月二十七日、前内大臣三条公忠の押小路(おしこうじ)殿で生まれた。父は北朝五代後円融天皇、母は公忠の娘厳子(通陽門院)。永徳二年(一三八二)四月七日

崇光天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一三三四 - 九八 一三四八―五一北朝在位。諱は興仁(初め益仁)。建武元年(一三三四)四月二十二日、光厳上皇の第一皇子として誕生。母は三条公秀の女、典侍秀子(陽禄門院)。のち徽安門院寿子内親王を准母となす。暦応元年(一三三八)光明天皇の皇太子に立ち

光明天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一三二一 - 八〇 一三三六―四八北朝在位。元亨元年(一三二一)十二月二十三日後伏見天皇の皇子として誕生。母は西園寺公衡の女広義門院藤原寧子である。翌二年二月親王宣下あり、豊仁(とよひと)と命名。建武三年(延元元、一三三六)六月

光厳天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一三一三 - 六四 一三三一―三三在位。正和二年(一三一三)七月九日、持明院統の後伏見天皇の第一皇子として一条内経の一条邸で生誕。母は前左大臣西園寺公衡の女寧子(のちの広義門院)。名は量仁。大覚寺統の後醍醐天皇の皇太子には、同統の邦良親王

長慶天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一三四三 - 九四 一三六八―八三在位。南朝第三代の天皇。名寛成。後村上天皇の皇子。興国四年(北朝康永二、一三四三)生まれる。母は嘉喜門院と考定される。晩年出家して覚理と号したらしく、同天皇の称号長慶院は禅宗寺院の一坊たる長慶院に

後村上天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一三二八 - 六八 一三三九―六八?在位。南朝第二代の天皇。後醍醐天皇の第七皇子。母は阿野公廉の女新待賢門院廉子。諱は義良(のりよし)、のちに憲良(のりよし)。嘉暦三年(一三二八)に生まれる。元弘三年(一三三三)後醍醐天皇が鎌倉幕府を

後醍醐天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一二八八 - 一三三九 一三一八―三九在位。正応元年(一二八八)十一月二日後宇多天皇の第二皇子として誕生。母は藤原忠継の女談天門院忠子。諱は尊治。延慶元年(一三〇八)九月十九日、持明院統の花園天皇の皇太子となり、文保二年(一三一八)

花園天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一二九七 - 一三四八 一三〇八―一八在位。伏見天皇の第四皇子(一説に第二皇子)。母は左大臣洞院(とういん)実雄の女、顕親門院季子。名は富仁。永仁五年(一二九七)七月二十五日誕生。正安三年(一三〇一)八月十五日、着袴の儀があり、同日親王宣下

後宇多天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一二六七 - 一三二四 一二七四―八七在位。名は世仁。文永四年(一二六七)十二月一日、亀山天皇の第二皇子として土御門殿で誕生。母は左大臣藤原実雄の女の皇后佶子(京極院)。翌五年六月親王宣下、八月立太子。当時院政を行なっていた後嵯峨上皇が

亀山天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
正嘉二年(一二五八)八月、兄後深草天皇の東宮にたつ、時に十歳。正元元年(一二五九)八月二十八日、十一歳で元服。同年十一月二十六日、父母のはからいで践祚、同十二月二十八日、即位。皇子世仁親王も文永五年(一二六八)二歳で東宮となる

後深草天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
寛元元年(一二四三)六月十日今出川殿で生まれ、二十八日久仁と命名、親王に立てられた。同四年正月四歳で践祚、父の後嵯峨上皇が院政を行なった。康元元年(一二五六)十一月母の妹公子(東二条院)が入内、翌正嘉元年(一二五七)正月中宮となった

後嵯峨天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一二二〇 - 七二一二四二―四六在位。名は邦仁。承久二年(一二二〇)二月二十六日誕生。土御門天皇の第三皇子。母は参議源通宗の女で典侍の通子(贈皇太后)。翌三年の承久の乱の結果、父の土御門上皇が土佐(のち阿波)に流されて以後は母の叔父の

四条天皇(国史大辞典)
一二三一 - 四二 一二三二―四二在位。諱は秀仁(みつひと)。寛喜三年(一二三一)二月十二日一条室町亭で誕生。後堀河天皇の第一皇子。母は藻壁門院藤原子(九条道家の娘)。同年四月十一日親王、十月二十八日皇太子となる

仲恭天皇(国史大辞典・日本大百科全書)
一二一八-三四 一二二一在位。順徳天皇の皇子。母は九条良経女の立子(のち東一条院)。諱は懐成(かねなり)。建保六年(一二一八)十月十日に生誕し、間もなく翌月二十六日に立太子。順徳天皇が後鳥羽上皇(順徳父)の討幕計画に熱心に関わり譲位したため

順徳天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一九七-一二四二 一二一〇―二一在位。諱は守成(もりなり)。後鳥羽天皇の第二(または第三)皇子として建久八年(一一九七)九月十日卯刻に生誕した。生母は、従三位式部少輔藤原範季を父とする重子(のち修明門院)、乳母は又従兄弟

土御門天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一一九五-一二三一 一一九八―一二一〇在位。諱は為仁。後鳥羽天皇の第一皇子。母は内大臣源通親女の在子(のち承明門院)、実は法印能円の女ともいう。建久六年(一一九五)十一月一日(または十二月二日)生まれる。同九年正月十一日、四歳で践祚

後鳥羽天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一八〇-一二三九 一一八三―九八在位。高倉天皇の第四皇子。母は修理大夫坊門信隆の娘殖子(七条院)。治承四年(一一八〇)七月十四日、五条町の亭に生まれた。この年五月には平氏打倒の兵を挙げた以仁王が敗死し、六月には遷都があって祖父後白河法皇

安徳天皇(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典・日本架空伝承人名事典)
一一七八-八五 一一八〇―八五在位。治承二年(一一七八)十一月十二日高倉天皇の第一皇子として誕生。母は平清盛の女の中宮平徳子(のちの建礼門院)。諱は言仁。十二月八日親王宣下をうけ、十二月十五日皇太子となる。時に生後一ヵ月余

高倉天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一六一-八一 一一六八―八〇在位。後白河天皇の第四皇子。諱は憲仁。母は贈左大臣平時信の女建春門院滋子。応保元年(一一六一)九月三日生誕。永万元年(一一六五)十二月親王宣下、翌仁安元年(一一六六)十月立太子。同三年二月十九日六条天皇

二条天皇(国史大辞典・日本大百科全書)
一一四三-六五 一一五八―六五在位。後白河天皇の第一子。諱は守仁。母は大炊御門経実の女贈皇太后懿子。康治二年(一一四三)六月十七日生まれる。鳥羽天皇の皇后美福門院得子に養育され、仁和寺覚性法親王の弟子となったが、久寿二年(一一五五)

後白河天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一二七-九二 一一五五―五八在位。大治二年(一一二七)九月十一日、三条殿で誕生。鳥羽上皇第四皇子。母は権大納言藤原公実の娘、待賢門院璋子。同年十一月雅仁と命名、親王宣下。近衛天皇の死去に伴い、久寿二年(一一五五)七月二十四日

近衛天皇(国史大辞典)
一一三九-五五 一一四一―五五在位。諱は体仁(なりひと)。保延五年(一一三九)五月十八日、鳥羽上皇の皇子として誕生。母は権中納言藤原長実の女得子(美福門院)。同年七月親王となり、八月早くも皇太弟に立つ。永治元年(一一四一)十二月

崇徳天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一一九-六四 一一二三―四一在位。諱は顕仁。元永二年(一一一九)五月二十八日、鳥羽天皇の第一皇子として誕生。母は藤原公実の女、皇后璋子(待賢門院)。保安四年(一一二三)正月二十八日、曾祖父白河法皇の意向により、父天皇の禅りを受け五歳で践祚し

鳥羽天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一一〇三-五六 一一〇七―二三在位。堀河天皇の第一皇子。母は大納言藤原実季の女、贈皇太后苡子である。康和五年(一一〇三)正月十六日、左少弁藤原顕隆の五条邸に誕生、その年六月親王宣下あり、宗仁と命名され、八月には早くも皇太子に立った

堀河天皇(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一〇七九-一一〇七 一〇八六―一一〇七在位。白河天皇の第二皇子。母は関白藤原師実の養女、皇后賢子(実父は右大臣源顕房)。承暦三年(一〇七九)七月九日誕生。同年十一月親王宣下あり、善仁と命名。応徳三年(一〇八六)十一月二十六日立太子


