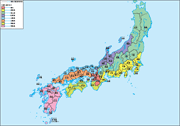第1回 「国」という地域──クニの原郷──
府県と「国」
本大系の特色は、地名項目を五十音順ではなく、地域ごとに取り上げたところにある。したがって項目を辿ればおのずから地域の特徴や地名間のつながりが見えて来る。これが五十音順配列方式だと、同じ地名あるいは同類地名の多少とか、地名としての共通要素といったことの理解は容易であり、その効用も大きいが、反面、近隣地域とのつながりは断ち切られてしまう。地名が地表に刻まれた地域の歴史であるとするなら、ひろがりのなかで地名を位置づける本大系の方式は地名理解の王道であろう。
その原則を府県ごとに適用したのが本シリーズであるが、それをさらに府県の母胎となっている国──律令時代以来の国。以後「国」と表記する──をベースにしたところに最大の特色がある。そのことの効用を理解するために、府県と「国」の対応関係を整理してみると次のようになる(但し歴史的経緯を異にする北海道と沖縄は除外)。
| (1) | 下野国が栃木県、近江国が滋賀県というように一ヶ国で一県を構成………13例 |
| (2) | 飛騨国+美濃国が岐阜県というように二ヶ国で一県を構成………9例 |
| (3) | 美作国+備前国+備中国が岡山県というように三ヶ国で一県を構成………3例 |
を基本形とし、他はそれのバリエーションである。
| (4)─1 | 一ヶ国の一部(郡単位)で一県を構成………9例 |
| (4)─2 | 二ヶ国それぞれの一部で一県を構成………1例 |
| (4)─3 | 一ヶ国+一ヶ国の一部とで構成………3例 |
| (4)─4 | 二ヶ国+一ヶ国の一部とで構成………5例 |
| (4)─5 | 三ヶ国+一ヶ国の一部とで構成………1例 |
| (4)─6 | 三ヶ国+二ヶ国の一部ずつとで構成………1例 |
というものである。これからも分るように(1)(2)(3)のケース、すなわち一ヶ国ないし三ヶ国で構成される県が過半数を占めており、「国」が基本的な構成単位とされたことがよく分かる。(4)の各種も、歴史的地理的な経緯から一ヶ国ないし三ヶ国と、それに一ヶ国ないし二ヶ国がそれぞれ分割され、その一部が付加されたもので、基本は「国」単位であったといってよい。これらに比し複雑な形をとるのが兵庫県の場合(上の(4)─6)で、但馬・播磨・淡路三ヶ国に丹波・摂津二ヶ国のそれぞれ一部をもって構成されており、当県が経験したさまざまな事情が反映されている。
以上は小学生の宿題にふさわしいような整理をしたまでのことであるが、しかし平素漠然と思っていたことがあらためて確かめられ、大いに勉強になった気分である。わが近代国家は廃藩置県によるあらたな行政区域の画定に当り、律令以来の「国」を基準に再編成されたことがよく分る。そしてこのことはベースとなった「国」が、古代律令国家が崩れたのちの政治的社会的変動、ことに中世の大名領国制や近世の幕藩制を経験したにも拘らず依然として生命を持ち続けたこと、換言すれば「国」がもつ地域性がある種の合理性というか妥当性をもっていたことを示している。それにしても「国」とはいったいなんであったのだろうか。その辺りのことを二、三のキーワードを通して考えてみたい。
「国」の領域
律令国家は最終的には全国に六六の国(ほかに二島)を建てるが、当初からそれが実現されたわけではない。当初は広域に首長(惣領とか大宰といった)を置いて管領させ、次第に領域を狭め、最終的に一国・一国宰(国守)とした。藤原不比等の下で大宝律令の編纂に従事した道君首名(みちのきみおびとな)も和銅六年(七一三)八月筑後守と肥後守の二ヶ国を兼任している。当時はこうした例が少なくなかったであろう。したがってそんな時期、行政の拠点となるべき国衙がどの程度整備されていたかも疑わしい。これまでの発掘調査によっても、国衙の施設で七世紀にまで遡りうるものはほとんどなく、多くは八世紀はじめに下ってからとされる。
立国の事例は八世紀に下っても見られるが、隣国から複数の郡を割いて立てたもので、実際には国の再編成という方がふさわしい。
| 和銅六年(七一三) | 丹後国(丹波五郡を割く)・美作国(同じく備前六郡)・大隅国(同じく日向四郡) |
| 霊亀二年(七一六) | 和泉国(河内三郡) |
| 養老二年(七一八) | 安房国(上総四郡)・能登国(越前四郡) |
| 弘仁一四年(八二三) | 加賀国(越前二郡) |
ちなみに最後の立国は九世紀の加賀国であるが、その理由は、加賀郡は国府から遠く人馬の往還が不便であり、それをよいことに郡司らが収奪を行なっている。部内が広大で巡検が困難なため、官舎の損壊や農桑の滞りがみられる、というものであったが、他の国でも同様であったろう。これは、時期は少し遡るが延暦一四年(七九五)九月、貢納上の不便解消と倉の延焼防止を目的として設けられた「郷倉」(郷ごとに設けられたのでその名がある)の設置理由(延焼防止はともかく)とほとんどかわるところがない。郡を割いて国を立てるか、郡郷の境界に倉を設けるかは、じつは紙一重の違いであったことを知る。「国」は、こうした手直しを繰り返えしながら行政区画として練り上げられて行ったのである。
さて国を立てるとはいくつかの郡をもって一定の境域を定めることであるが、具体的には境界を定めることに他ならない。その意味で古代国家の整備が加速された天武朝に境界画定の事例が目立つのは首肯されるところであろう。すなわち『日本書紀』天武一二年(六八三)一二月条に、諸王五位の伊勢王、大錦下羽田公八国、小錦下多臣品治、小錦下中臣連大嶋らが、判官・録史・工匠者をともなって派遣され、「天下に巡行して、諸国の境界を限分(さか)ふ」とあるのをはじめ、以後二、三年の間に画定作業が集中的に行われている。「国」の整備が中央集権体制をとる上での前提であったことを知る。
その境界の決定だが、日本列島の大半が山地である関係から、境界は山の尾根伝い、稜線をもってするのがほとんどで、これが基準的な画定方法となっている。三ヶ国にまたがることから三国岳(山・峠)などと呼ばれる山がけっこう多いのもそれである。この画定方法が大事なのは、多くの場合、稜線に囲まれた内部に地域的なまとまりを与えたことである。信濃・大和・近江などの国、なかでもその典型が近江国=滋賀県──先述の一国一県の例──ではなかろうか。
私事にわたるが滋賀県立大学在職時、近江文化論・環琵琶湖地域論を講ずるに当り、近江の地域性を考えたことがある。地図を見れば一目瞭然、四周を山で囲まれており、これほどの地域的な完結性がある「国」(県)も珍らしい(ただしその内部に全体の六分の一を占める琵琶湖があり、これは地域のつながりを阻害する要因ともなったが)。その完結性のゆえに近江国は、古来、その特性を生かした役割を与えられていた。近江国を通過する北陸道・東山道・東海道それぞれに関──愛発(あらち)・不破(ふわ)(関ヶ原)・鈴鹿の三関──が設けられ、天皇の崩御など政治的な緊張が生じた時に「固関(こげん)」されたのがそれである。三関がすべて国境の外側にあるのは、固関が外からの侵入に備えたものであることを物語るが、それは同時に、三関で囲まれた近江国そのものが全体として「防衛ゾーン」を形成したことに他ならない。
近江国はこのように極めて高い封鎖性を有する一方、古くから域内を三関に通ずる道が走っており、開放性も持ち合わせていた。近江国をもって「東西二陸の喉(のど)」と称したのは「武智麻呂伝」(『家伝』所収)のなかで藤原武智麻呂が近江守になった時の記述であるが、まことに近江国は東西の国ぐにから必らず通過しなければならない交通の要衝であった。この封鎖性と開放性をあわせもつがゆえに、国際的な緊張関係が昂まった時は近江国がクローズアップされ、遷都が行われた。白村江の敗戦後、中大兄皇子による近江京(大津京)遷都しかり、奈良後期、淳仁天皇を擁した藤原仲麻呂が突貫工事で造営した保良宮(北京)も、仲麻呂が強力に進めていた新羅出兵計画の拠点づくりのために平城京を離れた遷都といって間違いではない。もっともこの試みは、新羅による外交折衝に加えて、道鏡の登場という思わぬ事態の進展によりあえなく瓦解、保良宮は放棄され、いまはその跡も定かではない(村井・西川幸治編『環琵琶湖地域論』思文閣出版/二〇〇三年)。
国風・土風
「国」のもつまとまりは、このように主として自然的な条件に負うところが大であったが、それとともに「国」に関わる人間のさまざまな営為も無関係ではないと思われる。それにより国ぶりの文化が生まれ、それがまた「国」をより実体あるものにしたと思われるからである。
ここでもう一度道君首名に登場してもらおう。先述のように、大宝律令の編纂に従事し(遣新羅使を終えたあと)、筑後守となり肥後守を兼ねたが、赴任するや、規則をつくり、耕営はもとより菓菜の栽培や養鶏養豚を勧め、従わないものには厳罰主義で臨んだので、当初人びとは恨んだが、収穫時にその成果があらわれるや、喜んで首名に従うようになった。首名はまた肥後の味生(あじふ)池をはじめ各地に池堤を築造して潅漑をひろめた。いま利益を受けているのはすべて首名のお陰である、とは、『続日本紀』養老二年(七一八)四月一一日条にのせる卒伝の要旨である。自分も関わった律令に定める国守の仕事──「勧農・撫育」を地で行ったのが首名で、律令制度がどのようにして地方へ浸透したかがよく分る。すでに時代は原始蒙昧の段階ではなかったが、地方・地域の住民の啓蒙に当った首名の行為は、まさに古代における文明開化というにふさわしい。ちなみに右の卒伝の最後には、人びとは首名が亡くなると祀ったとあるが、いまも筑後から肥後にかけて首名を祭神とする小祠が点在しており、衆庶の間にひろまった首名信仰を見ることができる(村井『王朝風土記』角川選書/二〇〇〇年)。
平安末期の成立になる「国務条々事」(『政事要略』所収)は、中央から任国へ下る受領(国守)の心得うべき事柄を四二ヶ条にわたって書き上げたものであるが、そこには貴族の地方観と、その地方観を通して浮び上る、「国」を単位とする地域社会のあり方、地方住民の意識といったものが知られて興味深い。というのはこのなかには受領に対して繰り返えし地方の習俗習慣の尊重を説いているからである。
いわく、国境に入るに当っては在庁官人を召して「国風」を問うべし、いわく、境迎えの儀式は「土風」に従うのみ、いわく、新任国守の饗応は「国例」に従え、いわく、国庁での著座の儀式は公損がなければ「旧跡」を改めるな、いわく、老人に「故実」を尋ねるようにしたら善政といわれよう、などなど。個別の事例はともかく、それらに対処するのに「国風」「土風」「国の古風土俗」「国例」「国躰」あるいは「故実」「旧跡」に従うことを説く。同じ国守でも、人びとの思惑とは関わりなくおのれの信ずるところを実行した、律令形成期の首名と対極に位置するのが平安末期の国守(受領)たちであり、隔世の感がある。地域がその比重を増したことが、いまや中央による地方の掌握を困難にしているわけである。私はそうした時期における受領の地方観をもっとも端的に表わした言葉(諺)が「境に入れば風を問え」であったと考える。
先程一例としてあげたが、「国務条々事」のうち国庁における著座の儀式について、公損にならなければ「旧跡」を改めるな、という一条のなかに見る諺である。その国に入ったらその国の風を尋ね、それに従うようにせよ、との意である。誰しもがこの諺からすぐに連想するのは「郷に入れば郷に従え」であろう。意味するところは両者の間でさして変らないが、国境で任国の在庁官人たちと境迎えの儀式をするなど、緊張を強いられた新任国守にとって大事なのはまさしく「境に入れば風を問え」であって、この方が古態を示していると見る。そして対象が国境という結界から郷里という空間=集落へ移るところに、土風国風のいっそうの浸透と定着があったということであろう。その意味で「郷に入れば──」は「境に入れば──」の中世的変容を示す諺なのであった(村井前掲書)。
クニ──地域文化の視点から
この原稿を書いているさなか、お盆の帰省ラッシュがはじまり、書き終らないうちにUターンも終っていた。多分そんななかで「おクニはどちらで?」とか、「四、五日クニに帰ってくる」といった会話があちこちでなされたに違いない。帰省とはそのクニに向けてのいわば民族の大移動に他ならないが、それを惹き起こすクニとはいったいなんであるのか。
クニとはいっても、律令の「国」──私の場合でいえば周防国──のつもりで語っているとは思えないし、さりとて出身地の市町村を、郷里(のまち)とはいっても、クニとはいわないであろう。ここでのクニにあえて空間としてのイメージを求めれば、郷里以上「国」以下ということになろうか。知りたいのは、無意識にでも口から出てくるクニの母胎であり原郷である。
国とはその文字の成り立ちが示しているように、限りのある一区画のことである。したがって広くはない狭いところ、とイメージされている。丸茂武重氏も本居宣長や栗田寛のそうした説を引きながら、国の種々相を整理している(『古代の道と国』六興出版/一九八六年)。当然国には、相対的な意味で大小さまざまなものがあり、本稿でいうところの「国」もその一つである。しかし前述来のクニは空間的領域的概念というより、「国」を土壌として生まれた地域文化の概念といってよい。前に述べた、「国務条々事」に見るような「国風土風」が、まさにそれであろう。国風は「日本風」との意味ではなく「くにぶり」──地方的土俗的な習俗習慣を指し、地方・地域文化のことである。
「国」やクニの意味や両者の関係を考えるなかで見えてくるのは、クニ文化=国風文化の生成には地域の独自性ともいうべきものが必要であったという事実である。この国は政治的には中央集権的体制がとられ、中央優越・鄙蔑視の都鄙意識やそれに基づく社会的な諸関係が強く存在し続けていることは周知の事実であるが、それにも拘わらず、というより、そうであるがゆえに、国風土風が根強く存続し、地域社会が構成されて来た。そこには地方分権的な傾向さえ見られた。中央集権・分権とはなにか、抜本的に見直す必要を感ずる。ともあれ、そうした地方・地域の存在とそのあり方を「クニ」という言葉で表わすなら、「クニ」は「国」を母胎として生れた地域意識であり、地域文化の総体といえるのではなかろうか。
「国」「クニ」という地域の視点に立つことによって、これまでのステレオタイプの日本歴史の理解を崩し、あらたな歴史や文化理解の骨格づくりができるように思われる。その意味でも「日本歴史地名大系」の完結は、これからの歴史や地域の理解に刺戟を与え大きく変える起爆剤となるに違いない。
初出:『歴史地名通信』<月報>49号(2005年・平凡社)
該当記事は存在しません