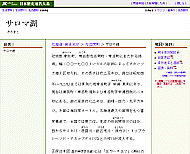第7回 アイヌ語地名の政治学(3)
(3)「アイヌ語地名」への転換
アイヌの歴史において「地名」も発達していった。アイヌ社会が蝦夷地の和人支配の環境の中に置かれて始まった「地名」の変化は、海岸部では遅くとも一五世紀にはおきていた。津軽海峡に面した辺りでは一二世紀ということもいえる。和人と接触する状況のなかで、和人とのあいだで地名を共有することは必要であったと考えられる。沿岸部では船の停泊地をトマリといい「泊」の字が当てられるが、日本語由来のトマリは一九世紀のアイヌには本来のアイヌ語だと信じられていた。
地名は和人によって文字に記録され、松前地(和人地)・蝦夷地の公称地名となる。それ以外の地名は通称地名(その呼称を知る者の死亡、その場所の変形、消滅やそれを記憶する者の忘却などとともに完全に失われることが多い地名)(注13)ということになるのである。しかし、アイヌの地名が失われる性質であることを論じるつもりはない。現代になっても、サロマ湖の古老が、昔は和人でもサロマ湖とはいわず、ただトーといったという報告がある(注14)のは、北海道では、通称地名に本来のアイヌの地名が残り、それが基礎的な単語であるためにむしろ消滅しにくい性質をもっている場合があることを暗示している。失われたのはアイヌの地名ではなく、アイヌ世界の構造なのである。地名が変化したり、あらたに創られるということでは「アイヌ語地名」もその結果として存在している。
地名の意図的な記録と地名の解釈は、蝦夷の地を領土化する一環として幕領期に進められた。地名は、蝦夷地を領土として把握するために製作が推進された地図に書き込む必要がある。未踏の地、つまり地名の空白地域を埋めるために、アイヌが和人の問いに答えるという形で「地名」は供出された。象徴的なのは安政六年(一八五九)の松浦武四郎「東西蝦夷山川地理取調図」である(注15)。
斜里のマクオイという地名は、源義経が張った幕のあとが土塁となった、と言い伝えていると松浦武四郎『知床日誌』に書かれているのだが、永田方正は「『シヤリ』ノアイヌ『ウンマタ』ト云フ者年既ニ八十余歳、同人云フ、余幼年ノ比、間宮林蔵ヲ見タリ、実父某曾テ云フ、地名ナキ処ハ間宮氏自ラ地名ヲ附シ地図ニ記載シタル事多シト。此『マクオイ』等モ間宮氏ノ附シタル名ナリト云フ、『マク』ハ和語ニシテ『オイ』ハアイヌ語ナリ」と暴露している(注16)。これが事実かどうか不明だが、たぶん、間宮はもともとあったアイヌ語を都合よく改作したのだろう。しかし、現地のアイヌには彼らの地名とはまったく別の次元のものと考えられていたことを、このエピソードは物語っているようである。
調査者が土地のアイヌに尋ねて返ってきた答えには、地形を説明する言葉にすぎず「地名」として存在していた名称とはいえないものもあった。その時点での臨時の命名であったことさえありうるが、「必ズ土地ノ実形ニ於テシ、敢テ苟モ虚名ヲ附スル者鮮シ」(注17)という名称であったから、記録された名称は別名はあっても異論はなく確定しやすかったのである。「アイヌ語地名」のアイヌ語は動詞を多用しているという性質があるが(注18)、それは「アイヌ語地名」が最初から地名のための名詞であったわけではないことを示しているのではないだろうか。この時点では、アイヌの地名は言葉として生きており、創造力をもっていたということもできる。しかし同時に、現在私たちが知る「アイヌ語地名」が成立した。「地名」が北海道の地名として記録されて日本語を唯一の国語とする政府の行政の道具となった時点で、日本国内の地名であっても日本語とは異質な「アイヌ語地名」という地位を与えられた。地形を表す名称は、アイヌの生活に必要な狩猟のための山歩きや移動の目標点や交通路の目安として使用されたはずであるが、記録されることによって固定化した時点で、地名としても成立した。それは言葉の形としての「アイヌ語地名」であって、アイヌの地名ではない、といういい方はひねくれているだろうか(注19)。
松浦武四郎はアイヌの道案内を連れて旅行しているが、その途次、地域の乙名を呼び出してそのあたりの地理を聞いている。たとえば「乙名カンレキを呼出し此辺の山道を聞試るに、此処の小沢を上りハシヨ子ツフまで行、其れよりフトロ領ミタレ岬の上え出る。凡朝五ツに出て夕七ツに下るによろしと」(注20)。これらの地名や時刻がカンレキの口から出た言葉そのままなのか、松浦のあてはめなのかは不明だが、カンレキの頭の中に地図が書き込まれているといえよう。交易や狩猟活動にともなうアイヌの行動範囲を考えると、冒頭に記したような「表現豊かな地図」が、書かれることこそなかったが太古から構想されていたとしても不思議ではない。しかし、そこに現れる地名はどういうものであったかといえば、本稿でアイヌの地名(「アイヌ語地名」ではなく)と呼んでいる性質の地名であっただろう。カンレキのような一九世紀のアイヌにとっての地名や地図の認識は、和人によるアイヌの土地の支配(地名の支配ともいえる)への対応を達成していたとみなすことができるのではないだろうか(注21)。
明治の半ば、永田方正が自著の緒言に「地名ノ原語ハ唯故老あいぬノ頭上ニ在テ存スルノミ。若シ故老あいぬ死スレバ地名モ亦従テ亡ブ」(注22)と記したのは、アイヌの地名が現実に存在するアイヌ世界と切り離せないという見解としては同感である。ただし、古老の地名伝承というものがあったかどうかについては疑わしい。古老はアイヌ語で考え語ることができるゆえに、言葉の意味を解説し、そこでの先祖の経験を語ることができるのであって、「地名」を伝承しているわけではない(注23)。地名にまつわる伝説がアイヌ社会にないとはいえないが、日本の地名の成り立ちにある、記憶していくために付けられる地名(注24)というものがアイヌ社会に存在し伝承されてきたとすれば、それはことさら記憶されなければならないという、アイヌ世界の変化にともなうものであったのではないだろうか(注25)。
本稿でおおげさに「政治学」としたのは、アイヌを和人が統治する関係になって地名に起きた力学的な変化をいうためではない。「アイヌ語地名の政治学」というと、アイヌの世界が和人のシステムに組み込まれて地名の文字表記が行なわれ、さらに漢字表記を経るなかでアイヌ語の意味やアイヌ世界が失われていった罪を検証し、アイヌ語地名を先住権の象徴と位置づける、というようなことが推察されるだろう。しかし、はじめは普通名詞にすぎなかった「地名」がアイヌ集団どうしや和人との関係性のなかで地名として育っていき、本来アイヌ語の論理で形成されたアイヌ語地名だからまさしくアイヌ文化として継承されてきたという事実が、「アイヌ語地名」の政治的な成長といえるのである。アイヌの人々の文化が地名という側面で、居住する地理的世界観のなかにおいて変容してゆくのも、政治的なことだといえるのではないだろうか。そこで、現在のアイヌと「アイヌ語地名」はどのようにかかわる現実があり、どうあるべきなのかという問題が浮上する。また、東北地方の「アイヌ語地名」に対しても、地名の言葉の解釈ではない歴史的な一考が迫られることになる。「アイヌ語地名」は、純朴なアイヌ世界の名残などではなく、歴史を経た姿なのである。
[注]
(13)千葉徳爾『地名の民俗誌』古今書院/1999年
(14)山田秀三『北海道の川の名 増補版』(前掲)、同『北海道の地名』北海道新聞社/1984年(復刊/草風館/2000年)等。なお、サロマ・トーの元来の意味は〈サロマペッの湖〉であったかもしれないと書いている。
(15)諸資料を集成して書き込まれた地名は、この「取調図」のように版本となったことによって地名としての権威をもつようになったのではないだろうか。しかし明治になって北海道の地名がどのような根拠で行政的に確定してゆくのかについては未考。地名解と地図作成については、佐々木利和「アイヌ語地名資料集成について」(『アイヌ語地名資料集成』草風館/1988年)参照。
(16)永田方正前掲書536ぺージ。句読点は筆者が付した。
(17)同上1ページ
(18)山田秀三「アイヌ語地名の話」『アイヌ語地名の輪郭』草風館/1995年(初出『角川日本地名大辞典』1北海道下/1987年)
(19)山田秀三は全著作中にアイヌ地名、アイヌ語地名、アイヌ語系地名という用語を使用している。これらを全く同義に使っていたのではないが、混用している場合もある。それらは地名の言語とその言語を使っていた人々は誰かという観点の用語であり、慎重を期した「アイヌ語族」という用語も使っている(「アイヌ語族という言葉」『アイヌ語地名を歩く』北海道新聞社/1986年参照)。私は「アイヌの地名」と「アイヌ語地名」に内容の差異を与えようとするのである。
(20)松浦武四郎『竹四郎廻浦日記』上/北海道出版企画センター/1978年/275ページ
(21)地名、地図に関する人類学的な研究として河合香吏「『地名』という知識――ドドスの環境認識論・序説」(佐藤俊編著『遊牧民の世界』講座生態人類学4/京都大学学術出版会/2002年)が興味深い。ウガンダのウシ牧畜民ドドスの地名の命名にはアイヌとも共通する普遍的な原則があることを確認できるが、彼らの知識からは約7800平方キロのドドスランドの詳細な地図を書き上げることができる。はるかかなたを見渡せる景観がその一因であるが、地名はその場所に身を置くことで確実に認識されるのであり、共有する地名に頻繁に言及することで共存の実感が保証されるという考察は共感できる。ドドスの場合はウシを追って人々が分散、移動する生活様式であるという条件である。
(22)永田方正前掲書2ページ。句読点は筆者が施した。ただし、この書は滅び行く先住民の文化としての地名を記録にとどめ地名解を施したものである。
(23)「この岬の、昔の名と今の名を言い解いて見ろ」(知里幸恵『アイヌ神謡集』岩波書店/1978年/86-89ページ)。これは、神謡で炉縁魚が小狼の神に向かっていった言葉であるが、切替英雄はアイヌが地名の由来に関心をもっていた例としてあげている(「頻出アイヌ語地名の形態論的構造」『アイヌ語地名研究』3/2000年)。小狼の神は、岬の名は昔は霊力に満ちていたので神の岬といったが今は霊力が薄まったので御幣の岬というと答える。続いて川の名を問われると、同じ理由で昔は流れの速い川、今は流れの遅い川というと答える。神謡におけるこのような問答の含蓄については熟考する必要がありそうである。また、トカチ生まれでありながらシコツ(ショコツか)アイヌという名の男に名の理由を聞くと「地名を以て名とする時は長寿するもの也」と答えた(松浦武四郎『近世蝦夷人物誌』)というのは興味深いが、他に例があるのか不明。
(24)千葉徳爾前掲書
(25)北海道にはアイヌ語perkeiぺレケイ〈割れている所〉が弁慶と結び付けられた地名がある。それは義経伝説から導かれた(上野智子『地名語彙の開く世界』和泉書院/2004年)わけではなく、義経伝説に先行する独自の回路があったと思われるが、アイヌ世界に組み込まれた地名伝説というジャンルのものは非常に限られている。口頭伝承と地名伝説との関係についてはあらためて考えてみたい。
初出:『歴史地名通信』<月報>50号(2005年・平凡社)
|前のページへ|
該当記事は存在しません