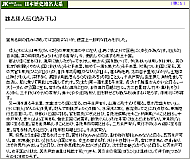第3回 転換期の考古学研究
── 弥生・古墳時代の畿内を一例として ──(1)
はじめに
ここ三〇年ほどで日本考古学は劇的に変貌した。道路や住宅団地などの建設、あるいは圃場整備といった開発工事に先行した遺跡の発掘調査が、その原因の一つであった。開発行為によって現地保存ができない遺跡は、次善の策として記録を残すための発掘調査を各自治体やその外郭団体が実施する、そうした「記録保存」のための発掘調査の日常化が、考古学研究を大きく変質させてしまった。
ピークだった一九九七年(平成九年)の発掘調査費用は約一三〇〇億円にものぼったし、調査に従事するための専門職員は九九年には七〇〇〇人に到達した。当然のことながら考古資料は急増したし、各種研究誌に発表される研究論文も膨大な数になった。その結果、考古学フロンティアは大幅に拡大した。文字史料のない時代はいうまでもなく、文字史料が遺された時代においても、それに描かれなかったさまざまな事実を浮かび上がらせたし、文字史料を遺さなかった北と南の文化様相も研究テーマとして俎上にのぼらせてきた。そして、生産遺跡・生活遺跡・墓地遺跡・宗教遺跡・政治遺跡等々、じつにたくさんの分野において多くの古代や中世、はたまた近世や近代の諸事象を明らかにしてきた。
いっぽう、わが国の歴史学界につよい影響を与えてきた唯物史観の凋落とポストモダン風思潮の流行は、自治体ごとに推進されがちな研究のありかたとも密接に関連して、考古学界にも地域性や多様性ばやりの論調をもたらした。そうした情況と相即不離に、いま考古学研究は細分化・個別化の一途をたどって、その全貌がいささかみえにくくなってきている。
さて、大地に遺された人間の労働の痕跡を遺跡・遺物というが、木簡や金石文などの一部を除くと、考古資料そのものはみずからの故事来歴を語ってはくれない。したがって、それらは歴史学にとっての一次資料というよりは、〇・五次資料とでもいうべき次元にとどまるにすぎない。そこで〇・五次資料の一次資料(史料)化といった作業がまず要請される。ものすごいスピードで不断に増えつづける資料、沈黙の資料をかかえた考古学研究のエネルギーの多くはそこに費やされてきたし、これからも継続されていくことだろう。
いっぽう、普通名詞にすぎない考古資料から歴史像を樹立しようとした場合、いまいくつかの課題が浮上しつつある。一つは、これまで日本考古学のパラダイムとして機能しつづけてきた「通説・定説」の類いとの関係のとりかたである。いま一つは、「原史」時代ともいわれたこともあった弥生・古墳時代での、文字史料と考古資料との関係のとりかたである。ここではそれらを意識しながら、おもに畿内地域の弥生・古墳時代を中心にして、奈辺に問題が所在するか、その一端を指摘しておこう。
I 文字史料と考古学
(1)魏志倭人伝と考古学
「景初三年」銘三角縁神獣鏡副葬の再評価と年輪年代法の成果があいまって、前方後円墳の成立年代が三世紀中ごろもしくは後半ごろまで遡及してきた。もっともここでいう前方後円墳は、奈良県の箸墓(はしはか)古墳(桜井市)や黒塚(くろつか)古墳(天理市)などのような定型化したものだが、それによって弥生・古墳時代の歴史像にも変更が迫られてきた。これまで弥生時代後期のできごとと理解されてきた邪馬台国は、一部古墳時代に重なる可能性がでてきた。そこで、二五〇年前後に死去したとみなされた卑弥呼の墓が、初期前方後円墳のなかでも墳長二八六メートルと最大規模の箸墓古墳である、との意見がつよくなってきたわけだ。
たしかにその蓋然性は高まってきたが、魏志倭人伝(『魏志』東夷伝倭人条)との障壁は依然として大きい。「径百余歩」という表現からすれば、直径一五〇メートル前後の円墳と認識されていたらしいが、箸墓古墳の墳丘との懸隔をどうみなすのか。また、「百余人の奴婢を殉葬させた」との記述があるが、そうした考古学的事実はいまのところ認めがたい。もっとも箸墓古墳の埋葬施設等は未調査だから一概にそうも断定できないが。しかし、それにしても魏志倭人伝にしたがうかぎり、箸墓古墳が卑弥呼の墓であることの可能性は低い、というよりは証明しがたい。なによりもこうした矛盾を、記述された大きさはその後円部にほぼ等しい、といった魏志倭人伝の「柔軟な解釈」で解消してしまうのであれば、文献史学と考古学の個別科学としての存立意義など、なきに等しくなってしまう。
邪馬台国に対立していた狗奴国についても、同様の問題を指摘しておかねばならない。古墳時代前期に、ことに東国に顕著なひろがりを見せた前方後方墳、もしくはその先駆形態の前方後方型墳墓の存在、ひいてはその分布範囲が狗奴国の版図だ、といった論調がある。弥生時代後期後半ごろはおもなものだけでも、出雲・伯耆などの四隅突出型墳墓、特殊器台・特殊壷をそなえた吉備の墳丘墓、丹後を中心とした方形墳墓、尾張・美濃・近江などの前方後方型墳墓というように、特定の墳墓様式を共有した複数の首長層の存在が抽出しうる。そうした事態が首長層の対立構造の反映だ、とみるのが前方後方型墳墓狗奴国説だ。
しかし、前方後方型墳墓を狗奴国の首長墓制だとすれば、邪馬台国のそれをあらわす墳墓はどれなのか、といった問題もでてくるがもう一つ、異なった墳墓様式をつらぬく共通項も無視しがたい。たとえば、四隅突出型墳墓の島根県西谷(にしだに)三号墓(出雲市)、双方中円型墳丘墓の岡山県楯築(たてつき)墳墓(倉敷市)、前方後方型墳墓の滋賀県神郷亀塚(じんごうかめづか)墳墓(能登川町)などの埋葬施設はいずれも木槨であった。中国起源のこの墓室構造は外部からは見えない。それだけに採用にあたってはつよい意志がなければ実現しがたい。前方後円墳出現前の墓制から各地の政治構造に論究しようとすれば、それらを通底した異質性と共通性の統一的な論究が必須となるだろう。
古墳時代には前方後方型墳墓の系譜をひいた前方後方墳が、東海・北陸・関東・東北一帯にひろがっていく。しかしながら第一、初期の前方後方墳は東国だけではなく、大和・山城・播磨・吉備などでも築造された。第二、その最大のものは、大和政権の本拠地につくられた大和(おおやまと)・柳本(やなぎもと)古墳群(天理市)にあった。第三、ほとんどの地域では前方後方墳は前方後円墳と共存していた。つまり、前方後方墳も円墳や方墳とおなじく、質量ともにその頂点をなす前方後円墳と一体的に考察しなければならないのである。
卑弥呼の墳墓、狗奴国問題についで、「倭国大乱」をめぐっての解釈も挙げておこう。北部九州勢力が掌握していた鉄資源をめぐっての南部朝鮮勢力との交渉権を、吉備勢力と連合した畿内勢力が二世紀後半ごろに武力で簒奪した、というのが通説的解釈であった。ところが、いま述べたような墳墓資料を見るかぎり、北部九州と畿内だけの二元論ではもはや前方後円墳出現前夜の政治情勢は語りきれない。西日本を主体とした日本列島各地では、いくつかの首長層の政治的まとまりが形成されていて、それぞれが相対的に自立した小世界を形成しながら、鉄素材などの非自給物資の交易をつうじて共存していた、というのが実情ではなかったか。なお、上述したのはいずれも邪馬台国畿内説にたっての理解であるから、そうでない見解に立てば解釈も大幅に変わってしまう。
(2)『記紀』と考古学
ほとんどの考古資料に固有名詞は付随しないから、描出された世界は普通名詞のそれである。しかし、想像を絶するほどの労働力が投入された大型前方後円墳の場合、「被葬者は誰か」という問いに解を提出したいという動機は否定しがたい。それはきわめて自然な問いだから、ジャーナリズムも古墳調査などに際して、識者の談話として頻繁にとりあげる。ところが、わが国の古墳は匿名性が大きな特質だから、どれも墓誌をもつことがない。だからいきおい、『日本書紀』や『古事記』に記された人物の比定が俎上にのぼってくる。前・中期古墳はともかく、記紀の編纂年代とさほど離れていない後期古墳や終末期古墳になると、ことに畿内では被葬者論争が一個のテーマにもなっている。
そうした研究を認めつつも、やはり墓誌でも出ないことには被葬者はわからない、という当然の立場を私はとりたい。どうしてかというと、その作業が編年体で叙述された『記紀』の思想を前提にしているからだ。はたして、『記紀』の記述はそのまま歴史事実なのだろうか。けっしてそうではないというのは、これまで厳密な史料批判にもとづいて切り開かれた地平がしめすが、そうしたなかで登場人物だけが歴史事実だ、とみなすのはどうも腑に落ちない。もう一つの疑念は、王妃や皇子が被葬者候補に挙げられるときである。その場合、古墳は首長墓だ、とみなしてきた立場とどう切り結ぶのか。あるいは、被葬者が複数であったとき「夫婦合葬」を想定したりするのと、どう整合性をもたせていくのか。ことは考古学の方法的一貫性に由来する。
「雄略朝」や「継体朝」といった呼びかたが、研究論文やシンポジウムのテーマで使用されることにも、おなじ理由で疑念をもつ。宮内庁に管理された天皇陵古墳の諸問題を指摘しつづけてきた考古学だが、天皇号の開始や漢風諡号などの文献史学の成果と、いったいどのようにかかわっていこうとするのか。『記紀』の陥穽に嵌ってはいけない。
そもそも前方後円墳をはじめとした古墳は、強固な共同性を属性にした墳墓である。ことに前・中期古墳はそうした傾向性がいちじるしくて、個人的色彩の副葬品はほとんどみあたらない。五世紀後半ごろになってやっと、金冠・飾履や装飾大刀のような属人的な威信財が副葬されだす。それは「黄泉戸喫」を象徴した須恵器・土師器の副葬と関連して、前方後円墳祭祀の変容を物語るものであった。それはともかく、考古学的には墳丘構造・埋葬施設・副葬品などの統一的分析をつうじての前方後円墳祭祀の内容、ならびにそれを媒介とした政治構造への究明が先決であるように思う。
律令国家を建設した支配層の正統的イデオロギー、それを捨象しては『記紀』のなかの「歴史事実」と向き合えない。しかし、そのイメージなしに考古資料だけで時代像が構築できるのかというと、それもおそらく難しい。これからは、考古資料の解釈と『記紀』のなかの事実にどれだけ整合性があるのか、といった観点からの研究も試行する価値はあるだろう。〈『記紀』を考古学的に読む〉といった営為になろうか。
|次のページへ|
該当記事は存在しません