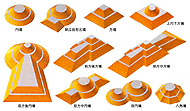第3回 転換期の考古学研究
── 弥生・古墳時代の畿内を一例として ──(3)
III 古墳時代の畿内
(1)前方後円墳国家を表象した前方後円墳
北海道・東北北部と沖縄を除いた日本列島──続縄文文化と貝塚後期文化は前方後円墳をつくらなかった──では、三世紀中ごろから七世紀初めごろにかけて、五二〇〇基もの前方後円墳(前方後方墳もふくむ)が築造されつづけた。そして、地域的な粗密はあるものの前方後円(方)墳のはじまりも終焉も、汎列島的なひろがりをもって展開した。そうした事実は、少なからぬ労働力を費消した前方後円墳が一般的な首長墓制などではなく、時‐空的に限定された座標軸のなかでの特殊な墳墓だ、といった視座を必要とする。
ところが前方後円(方)墳の造営をそのまま、その地域における首長の誕生と等値するかのような研究動向が、自治体考古学の隆盛と比例して勢いを増している。しかしながら、前方後円墳に代表された各地の首長墓系譜が安定した消長をみせるとはかぎらない。突然、消滅したり、また復活したり、ある時期だけ巨大化したり、前方後円墳から大型円墳に墳形変更したり、広範な地域を貫徹するかのごとき画期がみられたり、というふうに、とうてい個々の地域のなかだけでは解釈できない、各地の首長層の自律性だけでは理解しがたい事象が多々認められる。
〈画一性と階層性をみせる墳墓が前方後円墳〉である。前代からの伝統、技術的な限界性、中央からの距離感などに起因した地域的特殊性をもちながらも、墳丘構造や埋葬施設や副葬品の組み合わせに画一性をもたらしたのは、〈亡き首長がカミと化して共同体を守護するという共同幻想〉を内容とした前方後円墳祭祀であった。
いっぽう、大山(だいせん)(仁徳陵)古墳(大阪府堺市)の四八六メートルを頂点にして、墳長が二〇〇メートルを凌駕した巨大前方後円墳は全国で三五基しかないが、そのうちの三二基が大和・河内・和泉・摂津に集中している。墳長が一〇〇メートルを超えた三〇二基の大型前方後円(方)墳のなかの一四〇基は、それらに山城を加えた畿内に偏在している。そしていつの時期をとってみても、それぞれの最大級前方後円墳は畿内に築造されつづけたといった事実がある。それだけではない。三三面の三角縁神獣鏡を副葬した奈良県黒塚古墳のような多量の威信財、二〇〇本を超えた鉄槍を副葬した奈良県メスリ山古墳(桜井市)のごとき権力財の副葬量も畿内の古墳が圧倒していて、階層的秩序の頂点に畿内の首長層が聳立していたことは確実である。そうした特性をそなえた前方後円墳はけっして人里離れた、人跡未踏の地につくられたわけではない。生活空間を見下ろす丘陵や交通の要衝に立地したり、正面観をもったり、埴輪や葺石で墳丘を装飾したり、というふうに、ビジュアル性に富んだ墳墓であった。そしてなによりも、一人や二人の埋葬空間には大きすぎる墳丘をもっていた。
〈もの・人・情報の再分配システム〉を媒介とした、首長層の利益共同体のイデオロギー装置として前方後円墳は機能していた。各地の首長層はそれに参画しないと、鉄資源をはじめとした非自給物資が入手できなかった。そして、朝鮮三国などの外部勢力には軍事と外交で対抗する体制ができあがっていた。古墳時代の首長層が構築した、このような政治団体をどう概念づけるのか。
〈一定の領域をもって、軍事・外交・イデオロギー的共通性をそなえた首長層の利益共同体が前方後円墳国家〉である。そして、それを運営していたのは終始、大和政権(大和を中心とした畿内の首長層が担う)であった。すなわち、前方後円墳国家のメンバーシップを表象したのが前方後円墳であって、それは各地にひろがった前方後円墳連鎖として〈目で見る王権〉の役割を果たしたわけだ。
(2)前方後円墳国家を運営した大和政権
唯物史観の退潮は、それにほとんど依拠していた国家論の衰退をもたらした。考古学も同様で、ものいわぬ遺跡・遺物を使っての国家への論究はここのところ低調だ。それでも底流にあるのはやはり、一部の支配階級が多数の民衆を支配するための装置が国家だ、抑圧機構としての国家は克服すべきだ、といった史観であることは疑いない。ところが、既往の国家観でもっとも欠落しているのは、利益を共有した一つのまとまりを国家として把握する視座だと思う。内部的には階級社会であろうがなかろうが、軍事と外交で維持されていく領域をもった共同体を国家とみなす考え方である。もし、「もの」の所有をめぐって平等な社会ができたならば、唯物史観の国家観にしたがえば国家は死滅したことになるが、そうはならないのは現代の多様な国家をみればすぐに理解できることだ。
政治団体といった視点で国家を概念づけるならば、つぎにその運営方法を論究しなければならない。前方後円墳国家に関しては大和政権のありかたになるが、大和の大和・柳本古墳群、佐紀(さき)古墳群(奈良市)、馬見(うまみ)古墳群(奈良県北葛城郡・大和高田市)、河内の古市(ふるいち)古墳群(大阪府羽曳野市・藤井寺市)、和泉の百舌鳥(もず)古墳群(大阪府堺市)の畿内五大古墳群の分析が大きな手がかりを提供してくれる。
三世紀中ごろから四世紀後半ごろにかけての前期大和政権は、四~六人の大和の有力首長が大王を推戴して政権を共同運営していた。大和・柳本古墳群のほかにも、桜井茶臼山(さくらいちゃうすやま)古墳(桜井市)やメスリ山古墳のような巨大前方後円墳も併存していたから、大王といっても傑出した存在ではなかった。ついで、四世紀末ごろから五世紀後半ごろにかけての中期大和政権は、固定された四つの首長系譜から大王が輩出された。「倭の五王」の時代にほぼ重なった各時期の四人の有力首長は、各々が多数の中小首長層を統率して前方後円墳国家を共同統治した。誉田山(こんだやま)(応神陵)古墳(羽曳野市)の「陪塚」、アリ山古墳(藤井寺市)に副葬された一六〇〇本余の鉄鏃が示唆するように、中央政権は圧倒的な武力を具備していた。さらに五世紀末ごろから七世紀初頭にかけての後期大和政権は、有力首長の上位に大王が聳立していた。まさに「治天下大王」の時代であった。
王朝交替論と密接な関連性にあった、いわゆる河内政権論はどう評価できるのであろうか。大山古墳や誉田山古墳のような巨大前方後円墳が、五世紀には大和から河内(和泉)に遷移することを、それらを造営した政権の移動(簒奪)とみなすのがそうだが、そこでは佐紀古墳群と馬見古墳群が捨象されてしまっている。つまり、四世紀末ごろから五世紀後半ごろにかけての時期には、もはや終焉を迎えていた大和・柳本古墳群を除いた佐紀・馬見・古市・百舌鳥の四大古墳群で、墳長二〇〇メートル以上の巨大前方後円墳がそれぞれ一代一墳的に造営されつづけていた。いいかえるなら、どの時期をとっても墳長超二〇〇メートルの巨大前方後円墳が四基、畿内の四ヶ所で築造されていたという重要な事実を無視してはいけない。
河内政権論に象徴されるように、五世紀の中央政権を論究するとき、ともすれば佐紀古墳群と馬見古墳群が等閑に付されがちだ。一つの理由として、それらは天皇陵に治定された古墳をふくまない、もしくは少ないといった現代史が横たわっているのではないか。そうだとすれば、万世一系天皇制イデオロギーが無意識裡に考古学研究者を呪縛しているのかもしれない。なお中期大和政権の地方統治とかかわって、一三基ほど確認された韓国の前方後円墳についても論究しなければならないが、もはや紙数も尽きたので別の機会に委ねたい。
おわりに
〈概念化と体系化〉が、これからの考古学研究にもっとも要請される。権力・政治・国家・都市・カミ観念等々の概念を用いて、そして既往の多彩な理論を武器に膨大な資料のなかにわけいって、これからの歴史観の形成に貢献できる歴史像を樹立していかねばならない。そうした観点にたてば、学史のなかに研究課題はないことを銘記すべきである。それは私たちの日常生活のなかから抽出されるべきだと認識する必要がある。なぜならば〈結果としての現代の原因を過去に探る学が歴史学(考古学)だ〉。私たちの知的関心はなんといっても〈いま〉にあるからだ。
ここのところ、地域性や多様性が考古学研究の主流ともいえそうな、そして研究の目的とみなされがちな知的雰囲気が醸し出されている。あえてそれを否定するつもりもないが、そこではいきおい対象となった事象の「違い」が強調されがちで、ますます対象の細分化が進行して、ものごとの全体像が見えにくくなっている。「もの」に表象された「同じ」にも目を向けなければ、本質を見損なうことにもなりかねない。
地域性や多様性を超えたところでの〈われわれ意識〉や、人びとの統合への動向なども視野におさめた研究を指向しないと、見かけの華やかさとは裏腹に考古学研究は閉塞情況に堕していくと思われる。さしもの「記録保存」のための発掘調査も、一九九七年をピークとして急激に下降中だから、考古資料の歴史史料化への知的営為もなくなりはしないが早晩、勢いを失っていくと予測される。いっぽう、デジタル化の進行はますます情報の細切れ化を促進していくが、文脈のなかから切断された情報をもとにいかに時代や社会の動きを読みとっていくか、それもいまひとつの考古学研究の方法的課題であろう。なお月報であるため引用文献はいっさい省略した。ご寛容をお願いする次第である。
初出:『歴史地名通信』<月報>49号(2005年・平凡社)
|前のページへ|
該当記事は存在しません